1973年~ 低成長時代~バブル経済発生
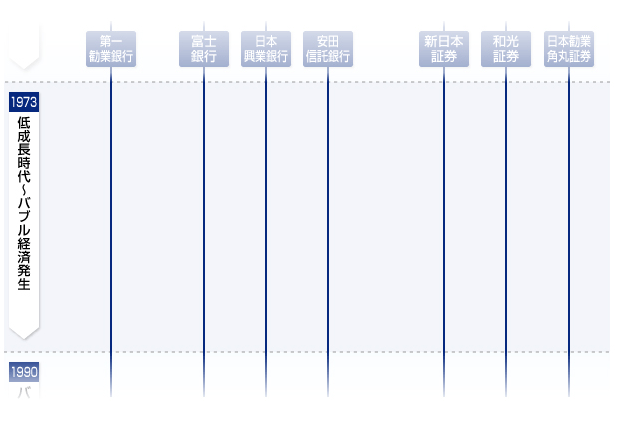
詳細
1973年、第一次石油危機が発生。翌年に経済成長率は戦後初めてマイナスとなり高度経済成長が終焉。
コンピューター時代の幕開けとオンラインシステムの進展により、銀行のお客さまの利便性向上に向けた取り組みが加速。
1969年
大型コンピュータと営業店を結び全国取引を即時処理するオンラインシステム完成
1971年
現金自動支払機によるオンライン・キャッシュサービスの開始
1972年
貯蓄・支払・借入の3つの機能をまとめた「総合口座」の取扱開始
1973年
店舗外キャッシュディスペンサーの設置開始
1984年
都銀13行によるCD・ATM共同利用サービス(BANCS)開始
ファームバンキング・ホームバンキングの試行的スタート
1980年代に入ると金融の自由化*、国際化が進展。邦銀各行は海外拠点を拡充していく。
- *金利の自由化(規制金利→自由金利)+金融制度の自由化
1983年
公共債の銀行窓口販売業務の開始
1984年
公共債ディーリング業務の開始

1985年
MMCや大口定期預金が登場し、自由金利定期預金の裾野が拡大
1994年当座預金以外の全ての預金金利が自由化
1980年代後半は、金融緩和を受けて内需主導の景気拡大が続き、株式や不動産への投資が加速、株価や地価が大幅に上昇し、バブル経済が発生した。事業会社の直接金融がエクイティファイナンスを中心に拡大、銀行は不動産を担保とした大型融資を拡大していった。
1988年
国際決済銀行(BIS)が自己資本比率8%の業務規制を決定
1989年
日経平均株価は最高値更新38,915円87銭(12月29日)