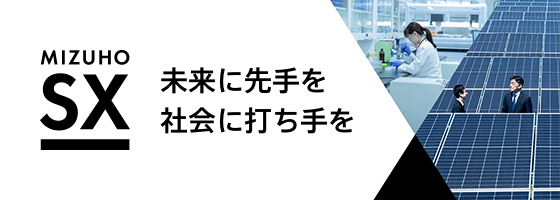「アカデミア×銀行データ」が日本の未来を変える。東大発のベンチャー企業と〈みずほ〉による新たな挑戦。
2025年1月20日
- BKみずほ銀行
OVERVIEW
政府や地方自治体がEvidence Based Policy Making:証拠に基づく政策立案(以下「EBPM」)を進める等、社会課題解決に向けてのデータ活用への機運が高まる中、〈みずほ〉は東京大学発のコンサルティング企業・東京大学エコノミックコンサルティング株式会社(以下「UTEcon」)との協業を開始。アカデミアと銀行データをかけ合わせて、ビジネスのみならず社会貢献にも挑戦しています。今回、プロジェクトに携わる2社の担当者たちにインタビューを実施。約4年に渡り続いている協業の裏側や両社の印象等について話を聞きました。
INDEX

左から佐藤 絵里子、瀬戸 雄太、皆川 直人(みずほ銀行)
UTEconと〈みずほ〉の取り組みは
社会やビジネスをどう変えていくのか?
近年、政府や地方自治体の動きの中で、注目を集めているのが、特定の事例や経験のみに基づくのではなく、データやエビデンスに基づいて政策の検証や企画立案を行うEBPMです。これは少子高齢化等により予算の制約を受ける中でも、政策の有用性向上のために実施されるものですが、データ活用や科学的な知見の導入は、ビジネスシーンだけでなく、国や行政といった領域においても拡がりを見せています。こうした世の中の変化をいち早くとらえ、社会やお客さまとともに成長をめざすために、〈みずほ〉でも2020年から国内銀行では初となるデータビジネス「Mi–Pot」を展開。法人や自治体を対象に銀行統計データ等と外部データを組み合わせた統計データの提供を行なってきました。
2021年には、行政や民間等のデータ活用で社会課題解決や都民の生活の質向上に資するプロジェクトを東京都が公募する「東京データプラットフォーム(TDPF)ケーススタディ事業※1」で〈みずほ〉がデータの提供を行なったことをきっかけに、東京大学が設立したベンチャー企業で、経済学・会計学・経営学等のアカデミックな知見に基づくコンサルティングサービス行うUTEconとの協業を開始。2023年には一般社団法人不動産流通経営協会による「口座情報を用いた物件管理状況の計測※2」を受託し、マンション管理組合毎の口座入金データを用いて、面積や築年数といった物件属性を前提とした「本来あるべき」入金額を予測するモデルを構築。また同年に内閣府による委託事業「令和5年度『リアルタイムデータを活用した経済動向分析(法人銀行口座データ活用)』※3」でもパートナーシップを結び、法人銀行口座データから経済動向の分析を行いました。
アカデミアと銀行データをかけ合わせることで、新たな領域に挑むUTEconと〈みずほ〉。この取り組みは、日本の社会やビジネスにおいてどのような意味を持つのか?約4年をかけて積み重ねてきた挑戦について、UTEconの柴田氏、渡辺氏、川原田氏、みずほ銀行デジタルマーケティング部の皆川、瀬戸、佐藤に話を聞きました。

銀行データを通じて社会貢献を。
アカデミアとの協業にかける〈みずほ〉の想い。
─UTEconさまとの協業前に、みずほ銀行が抱えていた課題はどのようなものでしたか。
皆川:我々デジタルマーケティング部では、「顧客利便性の徹底追求」を行うべく、法人・個人を問わずデジタルマーケティングの高度化に取り組んでいます。また、そのノウハウやデータを生かして、銀行業務で接点を有する様々なお客さまに対してアドバイザリー業務も実施しています。
その中でも銀行統計データをマーケティングに活用したサービス等を展開しており、一定の手応えを掴んでいました。一方、少子高齢社会で財政の制約も益々厳しくなることが見込まれる中、政府内でEBPMが着目され、みずほ銀行としても銀行データを通じて社会に貢献できるのではないか、との想いがありました。単にデータの加工や集計によって見える化を図るだけでも十分意義があります。しかし、政策の検証をする・政策立案に活かす、というレベルに達するには〈みずほ〉だけでは限界を感じており、データから深みのある洞察を引き出すには、その道のプロの知見やノウハウがないと根本的に価値のあるものは導き出せません。そのような中で他の社員から紹介してもらったのが、UTEconさまでした。
元々名前を存じ上げていた渡辺先生をはじめとした有名な先生方がいらっしゃり、計量経済学等のハードスキルはお墨付きです。そのうえ、実課題や社会課題を解くといったモチベーションと目線を備え、第一線で活躍する経済学・社会科学・工学等のバラエティー豊かな領域の先生方が在籍されています。我々のデータ等とかけ合わせると、うまくフィットするのではないかと考えておりましたので、協業の方向でまとまった際にはワクワクが止まりませんでした。
川原田氏:当社としましても、〈みずほ〉の皆さまとご一緒できることになった際の喜びは今でも鮮明に覚えています。
─銀行統計データのビジネス活用はメガバンクでは初めてですが、チャレンジに至った理由を聞かせてください。
皆川:2010年代にビッグデータやDXといったキーワードが叫ばれはじめましたが、当時からみずほ銀行としてもビジネス機会を伺っていた状況で、銀行データを活用して、新プロダクトやお客さまの課題解決につなげようとしていました。
瀬戸:金利を軸としたビジネス創出は我々のコアでもあり、様々な議論がされ尽くしています。しかし一方で、新たに何にチャレンジできるのか?という文脈もあり、データ利活用への関心の高まりとともに、我々が所属するリテール部門では統計データをサービスに用いていくことになりました。

左から渡辺 安虎氏、川原田 陽介氏、柴田 真宏氏(東京大学エコノミックコンサルティング)
自身のドメイン知識に捉われず、
ともに価値のあることを追求する。
─これまでの協業における、UTEconさまの役割や関わり方を教えてください。
柴田氏:基本的には、みずほ銀行さんのデータを使わせていただく形なので、一緒にクライアントさまと話しながら「どのような要件でどのようなプロジェクトを始めるのか?」というところを詰めていきました。UTEcon側としては分析に必要なデータの種別や要件をお伝えし、みずほ銀行側に確認いただくフローを取りました。難しい要件を提示させていただいたことは承知しておりましたが、分析を前に進められるデータをご用意いただけ、大変ありがたかったです。
─UTEconさまからの依頼を受けてデータを抽出する際に大変だったことはありますか。
瀬戸:UTEconさまとの案件は、かなり長い期間を遡って多様なデータを集める必要がありました。一方、我々の都合上、基幹システム移行前後だとデータレイアウトや仕様がかなり変わっています。新旧システムの仕様や背景を十分に理解していないと、データの解釈や処理が難しくなるため、過去と現在のデータを突合させていくプロセスが大変でした。
皆川:また、銀行ではデータが多岐にわたり細分化されているため、意味のある分析をするために分散しているデータの中から必要な情報を選定する作業を行いました。当部にはリテール分野のデータの有識者は多いのですが、我々の部門と接点がない部門が保有するデータについては、権限や情報が不足していました。社内で調整しデータを取得しましたが、ドメイン知識が不足していたこともあり、データの適切な解釈や抽出が容易ではありませんでした。
佐藤:銀行データの中には、個人情報保護や機密情報の観点から提供できないデータも多く存在するため、分析に必要な情報は残しつつ、特定ができない形に適切にマスキングする基準を設定するのにも苦労しました。
皆川:大変だったことを挙げるときりがないですが、自分たちのドメインに捉われ過ぎると、本当に価値のあることはできないと考えているので、こうしてデータを統合して利活用することに大きな意味があると思っています。
─協業を始めて約4年程経ちましたが、みずほ銀行にはどのような変化がありましたか?
皆川:やはり銀行データを使って社会的な課題を解決するという点は、1つの型になってきていると感じますし、我々のところで行政系の課題があれば、「UTEconさまにご相談させていただこう」という雰囲気になってきています。ケーススタディができたことで、当該領域におけるデータ活用に関する機運が高まったのではないかと考えています。
また、今までは「本当にこういった分析が銀行データでできるのか」との見方もありましたが、実績を積み上げていったことで、社内の見方も変わってきたと感じています。EBPM関連での銀行データ利活用に関する関心・理解度が高まったと言えるかもしれません。さらに、企業のお客さま等から銀行データに関心を持っていただくことが増え、実際にご活用いただいたお客さまからは感謝の声も届くようになりました。
瀬戸:我々だけでコンサルティングを提供させていただいていた時期もありましたが、自前主義のみでは包括的な課題解決に結びつけることが難しいと感じることもありました。一方、UTEconさまと協業させていただく中で様々な学びがあり、コンサルの1つの型が確立できつつあると感じています。また、当部としても、リテールのお客さま周りのデータだけでなく、法人のお客さま周りのデータ知見が高まり分析に活用できるようになった点が、この取り組みの中での学びとなりました。
佐藤:私はデータ提供を行う際の構築面でご支援させていただくことが多かったです。近年UTEconさまや他のパートナー企業さまに銀行データをお渡しして、共同で分析をする機会が増えています。そのため、セキュアな環境でのデータ連携方法や、データ仕様や内容を分かりやすくお伝えし、迅速に分析に取り組める環境をサポートしています。UTEconさまとの協業では、案件終了後のフィードバックが非常に有益で、データの提供プロセスが徐々に改善され、よりスムーズかつ効率的に対応できるようになりました。そのため、業務スピードも向上し、様々な企業さまと共同で多岐にわたる分析が行えるようになったというのが、この4年間での我々にとっての大きな変化です。
皆川:また、UTEconさまとの取り組みは、〈みずほ〉だけでできることではありません。業界やドメインの知識は〈みずほ〉にもありますが、関心のあるドメインに応じて、適切な経済学や関連領域の知見を適用することで初めて真に価値のあるものができると考えます。したがって、公共的な領域における銀行データ利活用×計量経済学というパターンでは業界をリードできているのではないか、と思っています。

データで社会課題に挑戦し続け、
これからも付加価値を生み出していく。
─みずほ銀行との協業について、UTEconさまはどのような印象を持っていますか?
渡辺氏:そもそもデータの質・量が他のプロジェクトと異なります。通常のプロジェクトでは絶対手に入らないような粒度で、膨大なデータを提供いただける。そのようなデータに対して深い分析を通じて付加価値を生み出す活動が行えることはまさに、経済学者冥利に尽きる経験です。また、有難いことに、みずほ銀行さんには環境をどんどん改善していただいて、当初と比べ、我々も格段にやりやすくなりました。データがきちんとメンテナンスされ、活用しやすい状態になっています。
データは保管されているだけでは、意味がありません。多くの企業では、どこかに保管されていても付加価値につながるような環境が整っていないことの方が多いです。データはあるものの、個人情報保護の観点で利活用が難しいものもありますし、法的にはOKであっても、「消費者心理を考えた時に本当にこのデータは活用しても良いのか?」という判断には、ステークホルダー間の議論が必要です。このような時には、重苦しい議論につながってしまうことが多いのですが、〈みずほ〉の皆さんは論点に関しても丁寧にロジックを積み上げながら整理されますし、前例主義にとらわれない環境構築も含めてプロジェクトをしっかりと前に進めていらっしゃいました。言うは易しですが、難易度の高いことに取り組まれており、大変感銘を受けました。会社としてあるいは個人として興味深い、といった観点を凌駕しており、世に広く付加価値を生み出せるポテンシャルを秘めている点において、社会的に大きな意味があることだと思っています。
─最後に、今後の展望を教えてください。
川原田氏:この4年間の協業関係を通じて、データの利活用により世に幅広く付加価値を提供可能な体制が構築できていると感じます。EBPMに取り組む政府をはじめ、データ活用に苦心している、あるいはイノベーションに挑戦したい企業さまには、ぜひとも、「みずほ銀行×UTEcon」にご相談いただきたいです。
皆川:この4年間の協業の中では、UTEconさまならではの観点で銀行データを分析し、行政課題の解決に活かすという事例を積み上げ、付加価値を示せるようになって参りました。
行政課題のみならず、マーケティング、医療・製薬等、各施策の効果検証が求められる業界においても、UTEconさまのようなコンサルティングが必要になると考えています。〈みずほ〉としましても、社会インフラを担う使命を持つ銀行として、データを活用して社会課題を解決するような取り組みを「UTEcon×みずほ銀行」の枠組みを通じて、これからも実践していきたいです。
PROFILE

みずほ銀行
デジタルマーケティング部マーケティング開発室データ分析チーム
皆川 直人
2011年みずほ銀行に入行。現市場開発部・みずほキャピタルマーケッツNY等で外国為替のクオンツ分析や米州でのデリバティブ規制対応PJ等を担当。公募留学を経て、2020年10月より現職にて、デジタルマーケティング高度化に関わる企画・データ分析、Google連携、データアドバイザリー業務、新規事業開発等に参画。

みずほ銀行
デジタルマーケティング部マーケティング開発室データ分析チーム
瀬戸 雄太
百貨店系システム会社、保険会社を経て、2017年よりみずほ銀行に入行。2018年より、Mi-Pot、データアドバイザリー業務に参画。

みずほ銀行
デジタルマーケティング部ビジネスディベロップメントチーム
佐藤 絵里子
2007年にみずほ情報総研(現 みずほリサーチ&テクノロジーズ)に入社。2008年にみずほ銀行へ転籍し、事務部門で銀行のトランザクションデータ分析や事務企画に長年従事。
2018年より、金融ビッグデータを活用した新規ビジネスの創出、推進業務に従事。

東京大学エコノミックコンサルティング株式会社(UTEcon)
代表取締役CEO
川原田 陽介 氏
ビッグデータ解析ならびに経済学者の知見に基づく事業最適化プロジェクトに豊富な経験を有する。東京大学経済学部卒業後、起業、ボストンコンサルティンググループ(BCG)コンサルタント、アマゾンジャパン合同会社シニアプロダクトマネージャー等を経て現職。

東京大学エコノミックコンサルティング株式会社(UTEcon)取締役
東京大学大学院経済学研究科及び公共政策大学院 教授
渡辺 安虎 氏
需要予測、価格戦略、サブスク設計、機械学習の応用、計量マーケティング等についての現場レベル及びマネジメントレベルでの実務的な経済分析経験を有する。また、法規制対応に関しては電子商取引分野及び不公正な取引方法に関する経済分析の経験を有し、企業結合等独占禁止法等に関する案件についても研究成果を活用したコンサルティングが可能。前職はアマゾンジャパン経済学部門長。ペンシルベニア大学PhD(経済学)。

東京大学エコノミックコンサルティング株式会社(UTEcon)
コンサルタント シニアアナリスト
柴田 真宏 氏
民間企業でのコンサルタントとしての勤務経験があり、クライアント企業の経営におけるデータの管理、分析、活用までの一連の流れを支援した。飲食店、製造業、サービス業でのマーケティングの効果測定および需要予測の経験を有する。東京大学修士(経済学)。
※所属は取材当時のものです。
文・写真/みずほDX編集部