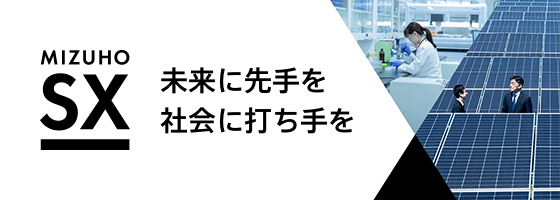なぜ〈みずほ〉はデジタルアセットに取り組むのか?
現場担当者が"ホンキ"と"ホンネ"を語る。
2024年12月12日
- FGみずほフィナンシャルグループ
- BKみずほ銀行
- TBみずほ信託銀行
- SCみずほ証券
OVERVIEW
暗号資産の仕組みでもあるブロックチェーン技術を使った既存資産のデジタルアセット化(=トークン化)。〈みずほ〉でも、会社の垣根を越え、グループを横断した活用の動きが広がっています。今回は、グループ各社からデジタルアセットに関わる現場担当者を集めて、これまでの取り組みや将来の見通しに加えて、そもそも「なぜデジタルアセットに取り組むのか?」について、座談会の形式で話を聞きました。
INDEX

左から小野 峰寛(みずほ銀行)、宮崎 龍三(みずほ銀行)
ブロックチェーン技術は、ゲームチェンジャーになる。
それぞれがデジタルアセットを知ったきっかけ。
─皆さんがデジタルアセットを知ったきっかけについて教えてください。
宮崎:みずほ銀行に入って2年目なので、今回のメンバーの中でいちばん若手です。最初に、暗号資産に興味を持ったのは大学時代。もともと投資に興味があって株等を勉強していましたが、当時ビットコインが話題になっていて、ちょっと買ってみようかなと思ったのがきっかけです。「ビットコインは今後、どんな値動きになるだろう?」と色々調べていくうちに、サトシ・ナカモトの「ディセントラライズド(decentralized:非中央集権型)」等、ブロックチェーンがもたらす価値観や思想を知り、面白みを感じるようになりました。大学時代は、ブロックチェーン関連のWEBメディアでインターンをする等、どっぷりハマっていった感じです。
星子:みずほ証券のリテールの部署にいたときに、オウンドメディアのWEBサイトを担当していました。その企画で京大大学院の岩下直行教授に会いに行き、暗号資産やビットコインについて詳しく聞いたことが最初ですね。興味を持って大学のフォーラムに参加する等して勉強しているうちに、「ブロックチェーンを使った金融が、ゲームチェンジャーになるかもしれない」と思い始めました。現在、株や債券は売買されても実際に決済するまでに2、3日かかりますが、セキュリティトークン(デジタル証券)やステーブルコインがあれば、リアルタイムに決済が完了することが可能になります。今はまだ課題もありますが、リアルタイム決済で時差や国境の壁がなくなっていく中、従来の金融機関はこのままの形で存続していけるのだろうかという危機感を持ちました。
緒形:私は仕事がきっかけです。2020年に金融商品取引法が改正されて、セキュリティトークンが登場し、2021年に三菱UFJ信託銀行が不動産セキュリティトークンの公募を実施しました。みずほ信託銀行で新商品開発の担当をしているので、研究のためブロックチェーンを使った金融について色々と勉強しましたが、そのうちに「不動産等、既存の流動化商品を大きく変えるかもしれない」と感じるようになりました。星子さんが「ゲームチェンジャー」と表現されていましたが、私も「今までにない金融商品が登場したな」という感覚がありました。
小野:イーサリアムの存在を知った2016年ごろから暗号資産に興味を持ち始めました。イーサリアムの「スマートコントラクト(smart contract)」という概念を知り、「お金にプログラムを内在させられるなら、お金の在り方が大きく変わるかもしれない」と思いました。当時は、ちょうど20年近く金融機関で働いてきて、改めて「お金って何だろう?」と思い始めていた時期だったんです。「これは面白い!」と思ったものの、当時の仕事は全く暗号資産と関りがなくて悶々としていたところ、社内のビジネスコンテスト「みずほGCEOチャレンジ」の募集がありました。そこで「暗号資産担保ローン」というアイデアをCEOにぶつけてみようと応募してプレゼンテーションしたのが、仕事でデジタルアセットに関わることになるきっかけになりました。業法の規制もありますし、社内ではまだ耳馴染みのないアイデアでもありましたが、「条件付き採用」を勝ち取り、〈みずほ〉のデジタル企画部に異動してデジタルアセット戦略を作る仕事に就くことになりました。

NFTから、不動産セキュリティトークンまで。銀行・証券・信託一体の「総合力」でプロジェクトを推進。
─現在、それぞれどのような業務に取り組んでいるのかを教えてください。
宮崎:私は、みずほ銀行のデジタルイノベーション部に所属して小野と近い仕事をしています。2023年9月に熊本県と共同で、ブロックチェーン技術のNFTやメタバースを活用して、地域の名産品「球磨焼酎」のブランド向上をめざす実証事業を担当しました。入社当初からブロックチェーンに関わる仕事がしたいと思っていたため、希望が叶って嬉しかったですし、先輩社員からも、新卒としてではなく、一人の担当者としてフラットに接してもらいありがたかったです。
緒形:私は、みずほ信託銀行の信託フロンティア開発部で新商品開発の担当をしています。2022年ごろから、ブロックチェーン技術を活用した不動産セキュリティトークンを商品化する仕事に関わっています。国内での不動産のセキュリティトークンは定着してきました※1が、それ以外の動産や航空機等、違うアセットを商品化できるかを検討中です。またブロックチェーン関連でいえば、ステーブルコインも法整備が進み国内で事業展開ができる環境になったので研究を行なっています。
星子:私は、みずほ証券のデジタルイノベーション部に所属しているのですが、緒形さんの部署と同じく、みずほ証券にもセキュリティートークンの発行に向けて発行体と一緒に取り組んでいる部署があります。私はその裏側で、金融庁や協会、関連する業界団体等の窓口や、社内の取りまとめ等を担っています。
小野:今回の座談会を企画したのが、私が所属するみずほ銀行デジタル企画部です。私は、グループ内でデジタルアセットに関する勉強会を開催したり、役員向けに説明資料や全体戦略をつくったりといった仕事をしています。今回の座談会のメンバーがそれぞれ、みずほ銀行、みずほ証券、みずほ信託銀行と異なる会社に所属しているのが、〈みずほ〉ならではの特徴だと思います。
星子:何か新しいことをしようと思い立った時には「あそこに相談しよう」と、すぐに会社の垣根を越えられる等、グループ内の横の連携はスムーズですよね。そこには、〈みずほ〉がこれまで様々な企業と合併をしてきた、歴史的な流れが背景にあるのかもしれません。※2「お互いにしっかり議論しよう」「相手のやり方や考え方を受け入れよう」と、納得感を伴った相互理解の上で仕事を進めていくカルチャーがあります。
緒形:私は2008年入社ですが、新人研修等もグループで行いますし、それぞれがお互いの持っている専門性に対して敬意を持っていますよね。2023年まで、〈みずほ〉のブランドスローガンとして「One MIZUHO」というものがありましたが、まさに銀行・証券・信託が一体となってプロジェクトを進めるカルチャーがあると思います。
宮崎:〈みずほ〉の人たちは「できるからやる」というよりも、まず「お客さまにどのようなメリットがあるのか?」から考えますよね。きちんと設計した上で商品を出していかないと、お客さまとの信頼関係に良くない影響がある。ブロックチェーンに関連した新商品も、しっかりと「お客さまにとってどうか」を考えながら議論していかなければいけない分、時間を掛けて進めている印象です。
小野:私は長く営業にいましたが、確かに「お客さまにとってどうか」を最初に考えるカルチャーが浸透していますね。
緒形:その分、皆が納得してお客さまもメリットがあると確信し、グループ全体で「やる」と決めたときの推進力は大きいと思います。
星子:まさに「これから」ですね。銀行・証券・信託の「総合力」で言えば、私も〈みずほ〉が一番だと思います。

左から星子 哲徳(みずほ証券)、緒形 千恵(みずほ信託銀行)
「信託」の起源は中世ヨーロッパ。お客さまとの「中長期のお付き合い」をブロックチェーンで実現する。
─今後、金融業界においてデジタルアセットはどのように展開していきますか?
星子:先ほど、金融業界にとって「デジタルアセットやブロックチェーンがゲームチェンジャーになる」という話をしましたが、いよいよ始まる予感がしています。私はみずほ証券に入社してから30数年ですが、これまでも大きな変化がたくさんありました。いわゆる日本の「バブル崩壊」直後の入社になりますが、当時はお客さまと対面で会話していました。2000年前後になりインターネットが普及すると、証券会社のリテールでの販売はネットが主力になりました。店舗でなければ見られなかった金融商品の値動きや、企業の決算もネットで閲覧できるようになり、最近ではスマートフォンが1台あれば、情報はもちろん取引もどこでも行うことができます。インターネット登場から20数年が経ちますが、デリバティブや暗号資産、セキュリティトークン等、新しい技術が登場することで、どんどん新しい商品が登場しています。これからはブロックチェーン技術で国境を簡単に越えられるようになり、取引の透明性も高まるので、金融業界にとっては大きな変化が訪れるのではないでしょうか。
緒形:ブロックチェーン上にあるトークン化された金融商品であれば、「つながりが見える」のも革新的だと思います。そもそも「信託」という言葉の起源は中世ヨーロッパだという説があります。兵士が戦争に行くときに信頼できる人に土地を管理してもらい、その利益を兵士の家族に渡してもらうのが「信託」です。この信頼のつながりを、デジタル上に持ってこられるのがブロックチェーンの技術です。これまで不動産の証券化は、発行して管理するコストが大きいので「REIT(リート)」のように大きな金額のものしか扱えませんでした。しかし、セキュリティトークンは比較的低コストなので発行額を小口化することができ、たくさんの個人投資家の方々に販売することができるようになります。
星子:まさに。わかりやすく言えば、紙の契約書だと50人に販売すれば50人に送らないといけないところですが、ブロックチェーン等の自動化技術があれば、金融商品の販売が一気に効率化されるんですよね。
緒形:管理コストでいえば、例えば株主の名簿は信託銀行でお預かりしますが、これまでは紙で管理されていました。今はデジタルになり、さらに今後ブロックチェーンのような分散台帳で管理されるようになってくると、コスト削減以外のメリットも出てきます。
将来的には、セキュリティトークンで長期保有していただいているお客さまに裏付資産に関連する優待やポイントを差し上げる等、これまでできなかったサービスを投資家の皆さまへ提供できるようになります。「信託」は「信じて託する」ですから、もともと中長期にわたってお付き合いするものです。これまでは、発行体の皆さまには中長期のお付き合いができていても、信託がキーとなった形では、投資家の皆さまにうまく提供できていなかったんですよね。

地方創生こそ、トークン化の発想があっていい。音楽やスポーツ、自動車から電力まで「金融」の世界が広がる。
─具体的に、金融領域でどのようなトークンの活用方法が考えられますか?
緒形:「不動産セキュリティトークンを地方創生に活かせないか」というお客さまの声は多くあります。東京や大阪等の大都市圏のビルであれば、金額も大きいので機関投資家向けに資金調達をすればいいのですが、例えば地方の駅前のビル等はそうもいきません。一方で、地方の駅前のビルは地元の人にとっては生活の一部になるので、不動産セキュリティトークンとして保有したときの愛着が異なります。不動産セキュリティトークンが小口化して流動性が上がり、もっと一般の人たちにとって身近なものになれば、地元の人が「生活にとって大切なビルだから」とその場でトークンを購入してくれるかもしれません。実際に、ふるさと納税では、そうした取り組みが広がっていますよね。さらに配当だけではなく、ポイントや地域通貨のようなもので返せば、地域の活性化にもつながります。
「クラウドファンディングでいいじゃないか」という声も聞きますが、トークン化(情報をブロックチェーン上のトークンに置き換えて保存・利用する技術)にはコスト削減のスケールメリットがありますし、〈みずほ〉のような金融機関が提供することによる投資家への安心感は大きいと思います。
小野:愛着のあるものや、皆が好きなものが、トークンとして金融商品になっていく流れはとてもいいと思います。私は趣味で音楽をやっていますが、音楽には最新ヒットチャートがありますよね。昔はランキング上位の楽曲を聴く人が多かったと思いますが、今は「押し付け感」みたいなものを感じる人が多くなっているような気がします。「推し活」もそうですが、それぞれが好きなものを追求できるほうが楽しい。トークン活用のヒントは、このあたりにあるような気がします。
緒形:実は、私も音楽をやっているのですが、日本だと「音楽ホール」が少なくなってきているんですよね。地方を含めて建物の老朽化で「建て替えをどうするか」という話がたくさんあります。音楽が好きな人たちにとっては「自分ごと」でもあり、そうした資金調達の課題にはトークン化して小口の金融商品にしたほうが、お金を集めやすいのではないかと思います。
宮崎:会社で誰にも話したことがないのですが、私も実はボクシングをやっていまして…。
全員:えーっ、知らなかったです。
宮崎:スポーツにトークンを活用するのもいいですよね。ボクシングをやっているうちに面白くなってきて、最近では知り合いの試合を観戦するようになりました。そこで気づいたのは、試合するには場所が必要だということです。ボクシングに適したサイズのスタジアムやアリーナ等の施設は少ないと思いますので、音楽ホールと同じように応用できそうですね。
星子:自動車も、今はパソコンのように通信してソフトウェアが更新することで、新しい機能が追加される時代です。EV(電気自動車)が走りながら充電する技術も開発されていますし、家でも太陽光発電が増えています。EVが巨大な蓄電池だとすれば、電力が高いときに売って安いときに買う等の「電力取引」に、トークン化の考え方が入っていくこともありそうです。AI(人工知能)も発達していますので、自動化してコントロールを任せることもできるのではないでしょうか。
小野:音楽やスポーツ、自動車から電力まで、いろんな金融商品を自分の好みによって、アラカルトで選べるようなものになっていくと面白いですね。
星子:こうやって時代が変わっていくときに、技術があってもお金がついてこないと回りません。何があっても「金融」という機能は、社会にとって必要だと思いますね。
PROFILE

みずほ銀行
デジタルイノベーション部
宮崎 龍三
2023年にみずほフィナンシャルグループ/みずほ銀行に入行。学生時代にブロックチェーン関連の企業でインターンをしていた経験から、入行後もブロックチェーンを活用した新規事業の創出に従事。現在は各企業との共創推進のほか、デジタルアセットの〈みずほ〉全社戦略の策定も担当。

みずほ証券
デジタルイノベーション部
星子 哲徳
1994年旧新日本証券入社、リテール営業、市場部門、企画セクションでの旧みずほ証券との合併作業等を経て、非対面チャネルの所管部署に異動。為替証拠金取引の導入、オウンドメディアの開始、Webマーケティング等を担当。2018年より現在の部署にてデジタル証券や社内のDX推進、業務効率化・高度化等の業務を担っている。

みずほ信託銀行
信託フロンティア開発部
緒形 千恵
2008年みずほ信託銀行株式会社入行、不動産仲介業務に従事。不動産アセットマネジメント業務、私募ファンド運用業務、ファンド開発営業を経て、2014年より現職。地域金融機関との連携拡充に資する新商品・サービス開発等に従事。現在はセキュリティトークン等デジタル証券関連商品のプロダクトマネージャーとして企画・立案を推進。

みずほ銀行
デジタル企画部
小野 峰寛
2003年みずほ銀行入行。みずほ銀行/みずほ信託銀行での個人向け本部企画・営業店での法個人担当を経て現職。2023年、社内ビジネスコンテスト「GCEOチャレンジ」にて「暗号資産担保ローン」提案が契機となり現部署へ異動。みずほフィナンシャルグループ全体のデジタルアセット戦略立案を担う。
※所属は取材当時のものです。
文・写真/みずほDX編集部