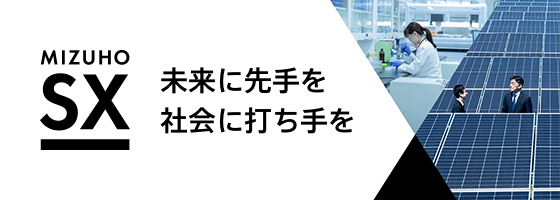左から三浦、加藤、住谷(みずほフィナンシャルグループ)
資料作成はAIに任せよ。
〈みずほ〉が挑む、“バイブ・ドキュメンティング”とは?
2025年8月20日
- FGみずほフィナンシャルグループ
OVERVIEW
〈みずほ〉では、生成AIの利活用を全社的に強化し、業務の効率化と高度化を加速させています。本記事では、その最前線の事例として、社員の思考の断片からAIが資料を自動生成する、文書作成業務の抜本的改革「バイブ・ドキュメンティング」の挑戦について、取り組みを進めるデジタル戦略部のメンバーの生の声とともにお届けします。
INDEX
AIが雰囲気(Vibe)を読み取り資料を作成?
「バイブ・ドキュメンティング」がめざす真の目的。
金融業界では長年、文書作成をはじめとする膨大な定型業務が、社員の創造的時間を奪ってきました。この根深い課題に対し、〈みずほ〉は2025年6月より「Work with AI@MIZUHO」という新たな社内浸透施策を開始。社員一人ひとりがAIとともに働き、業務効率化と創造的な働き方を実現することで、仕事やサービスの質を向上させる取り組みが始まっています。
その一角を担うのが、AI研究者のアンドレイ・カーパシーが提唱した「バイブ・コーディング」の概念にインスパイアされた「バイブ・ドキュメンティング」です。
デジタル戦略部長の藤井は、この取り組みの背景をこう語ります。
藤井:多くの社員が会議資料の作成といった文書関連タスクに多大な時間を費やしている実態は、私たちにとって長年の課題でした。これでは、社員が本来発揮すべき専門性をいかしきれていない。「文書作成に費やされる時間」を、いかにしてお客さまのための価値創造や新たな戦略を練る「思考の時間」へと転換するか。これは経営レベルで議論されてきた重要なアジェンダです。こうした強い問題認識から取り組みが始まりました。
「バイブ・ドキュメンティング」とは、いわば“思考の翻訳機“。人間は思考の断片や問いかけのラフなメモ、ブレストでの発言といった「Vibe(雰囲気や空気感)」をインプットするだけで、AIがその意図を汲み取り、構造化され、形式整備されたドキュメントを自動で生成します。
ただし、単にAIに文書を「作らせる」ことが目的ではありません。定型的な作業をAIに任せることで、人間は分析、判断、対話といった本来の価値創造に集中する。これが私たちのめざす姿です。
| 旧来の「形式重視型ドキュメント」 | 新しい「バイブ・ドキュメンティング×AI支援型」 | |
| 目的 | 正確性・網羅性・形式遵守 | 意図伝達・思考拡張・スピード重視 |
| 作成者の負担 | 大(書く=考える+整える) | 小(書く=思考のメモ+AIに整えてもらう) |
| 作成時間 | 長時間(レビューも重層) | 短時間(AIが構造化・補完) |
| 思考のスタイル | 完成品を出すために書く | 考えながら書く、書きながら考える |
| AIの使い方 | 校正・要約程度 | 思考整理、構成案、図表化、反論生成等の高度支援 |
この取り組みの核心は、単なる市販ツールの導入ではなく、業務プロセスそのものを見直し、現場の課題を解決するAIツールを内製で開発・適用している点にあります。デジタル戦略部では、個々のツール開発にとどまらず、それらを業務フローに沿って創造的に組み合わせる等、先進的な活用が進んでいます。
デジタル戦略部次長の冨澤は、〈みずほ〉独自の内製ツールについてこのように語ります。
冨澤:個々のツールの力を最大限に発揮するには、業務フローを理解し、適材適所でツールを組み合わせることが重要です。例えば「情報収集→分析→文書化→共有→フィードバック」という流れの中で、各ステップに最適なツールを配置します。
市販の汎用AIツールと異なり、〈みずほ〉の内製ツールは金融業務に特化した設計が特徴です。金融特有の用語、規制環境、業務フローを理解し、〈みずほ〉独自の業務プロセスに最適化されています。効率化だけをめざすなら外部ベンダーのソリューションもありますが、私たちは業務の本質を理解したツール作りにこだわっています。それが単なる効率化を超えた価値創造につながると信じているからです。
冨澤が説明するように、〈みずほ〉では業務に即したツールの構築を進めています。ここからは、この取り組みの可能性を示す、最前線の3つの挑戦をご紹介します。

画像内のシステム情報は実在するものではなく、イメージです
【挑戦①】レガシーコードの可視化により、見えない資産を組織の知恵に変える。
デジタル戦略部の三浦が直面したのは、ドキュメント不足の大規模なSAS(統計解析ソフトウェア)プログラムの理解と改修という課題でした。何年もかけて複数の担当者によって修正されてきたこのコードは、過去の担当者からも「触らないほうがいい」と言われる一方、規制対応のために修正が必要な状況で、そのために1からプログラムを解析する必要がありました。
通常、このようなレガシーコードの理解には数週間を要しますが、三浦は内製AIツールを創造的に活用し、わずか1日でこの課題を克服しました。
三浦:プレゼンテーション資料作成用のAIツールは、本来テキストからスライドを生成するツールです。これを応用し、大量かつ複雑なプログラムをインプットしたところ、コードの構造を見事に可視化してくれたのです。その後、対話型AIを使ってコードレビューを行うことで、短期間でレガシーコードの改修を実現。さらに議事録作成AIを活用することで、チーム共有を効率化しました。従来なら数週間かかる作業が1日で完了したうえに、個人の理解だけでなくチーム全体の共通認識として確立できました。
三浦はこのように振り返ります。この取り組みの価値は、単なる時間短縮だけではありません。属人化していた知識を可視化し、組織の資産として共有可能にしたことが最大の成果です。また、プレゼンテーション資料作成用ツールをコード可視化という想定外の用途で活用した創造性も、今回の取り組みのポイントの1つです。
この事例をきっかけに、他のアプリケーションへの応用や、更なる創造的な使い方の検討を進めています。
【挑戦②】開発の効率化にとどまらない、自己発展的サイクルの構築。
議事録作成AIツールの機能拡張を担当するデジタル戦略部の住谷は、アイデア出しから要件定義、テスト仕様書作成までの工程に時間を要することに課題を感じていました。
住谷:迅速な機能拡張を実現したい一方で、これらの作業に数週間程度かかってしまっており、スピード感に課題を感じていました。そこで、私たちが開発しているAIツールを自分たちの開発プロセス自体に活用できないかと考えました。
この考えから住谷は、3つのAIツールを連携させた独自のワークフローを構築。具体的には、対話型AIを使ってアイデア出しと壁打ちを行い、それを基にチーム内でディスカッションを実施。ディスカッション内容を基に、議事録作成AIを活用して要件定義をまとめ、文書作成AIで要件定義書として形式化。さらに対話型AI、文書作成AIでテスト仕様書を作成することで、これらの作業を1日で完了させました。作業の効率化を実現するだけでなく、テスト仕様書の網羅性も向上し、人間が見落としがちなエッジケースまで考慮された高品質な成果物を作成することができました。
住谷:複数のAIツールを業務フローに合わせて組み合わせることで相乗効果が生まれました。特に「発散→収束→形式化」というプロセスに沿ったツールの使い分けが効果的だと感じました。
住谷は今回のワークフロー構築についてこう振り返ります。この取り組みは「自己発展的サイクル」と評価しています。自社開発したAIツールを使って、そのツール自体を進化させるという好循環が生まれたのです。
この事例も、前述の事例同様、議事録作成AIを議事録作成だけではなく、要件定義に活用するという発展的な使い方をすることで、大幅な作業効率化と作業品質の向上を実現することができました。これにより、ユーザーニーズをより迅速に製品に反映することが可能になりました。
【挑戦③】対話時間の創出と提案力の向上により、営業活動の質的転換をめざす。
ここまでは、AIツールの連携や創造的な活用によって、開発プロセスそのものを変革した事例をご紹介しました。最後に、こうした思想をさらに発展させ、お客さまと向き合う営業の最前線に大きな変革をもたらそうとしている、未来志向の挑戦をご紹介します。
4年間の法人営業経験をもつデジタル戦略部の加藤は、今、かつての自分が感じていた課題の解決をめざして営業支援AIの開発に取り組んでいます。
加藤:法人営業担当の業務のうち、お客さまとの直接対話の時間は意外にも全体の15~20%程度しかありません。残りの多くは情報収集や資料作成に費やされています。この状況を変えて、お客さまとの対話の時間をもっと増やしたい。営業担当として日々業務を遂行する中で感じていたこの思いが、今の私のモチベーションです。
このような思いを持って加藤が開発を進めているのは、業界情報収集やお客さまに合わせた提案資料作成等、訪問前の準備作業をサポートし、営業担当の思考を加速させる"最高のバディ"となるAIツールです。
加藤:AIが作る提案は、どうしても教科書的になりがちです。しかし、本当にお客さまの心を動かすのは、その企業の状況に深く寄り添った提案です。だからこそ私たちは、AIエンジニアだけでなく、私のような業務経験者も開発に参加することが重要だと考えています。現在、現場の営業担当者たちへのヒアリングを重ね、彼らの思考プロセスや好事例の解明を進めています。こうした現場の肌感覚をシステム開発に反映できることは、〈みずほ〉の内製開発の大きな強みです。
将来的には、過去の優れた成約事例をAIに学習させ、企業の成長ステージや課題に応じた最適な提案の切り口をサジェストできるようにしたいと考えています。このツールは、特に経験の浅い若手営業担当者にとって、強力な武器になるはずです。
このように未来を見据える加藤は、このAIが完成すれば、資料作成時間は劇的に削減され、創出された時間でお客さまとの対話の質と量を飛躍的に高められると確信しています。まだ道半ばの挑戦ですが、その先には、営業活動の質的転換という大きな果実が見えています。
効率化を超えた業務変革により、新たな価値を創造。
先行事例から見えてくるのは、AIツールが単なる効率化を超えた価値を生み出す可能性です。それは大きく3つの側面から捉えることができます。
1つ目は、「専門性の解放と創造的業務への集中」です。デジタル戦略部内の調査では、AIツールを活用した社員の90%以上が「創造的な業務に使える時間が増えた」と回答しました。AIが定型的作業を担うことで、社員は本来もつ専門性を発揮し、価値創造に充てる時間が増えているといえます。
2つ目は、「組織知の活用と知識共有の促進」です。従来は個人の経験や暗黙知に依存していた業務知識が、AIツールを通じて組織全体で共有・活用できるようになっています。レガシーコード可視化の事例は、まさに「見えない資産の組織知化」の好例です。AIツールを介した知識の構造化と共有は、組織の持続可能性を高める重要な取り組みです。
そして3つ目が、「データドリブンな意思決定の実現」です。「バイブ・ドキュメンティング」の思想は、勘や経験に依存しがちな業務を、よりデータドリブンなものへと変革する可能性を秘めています。AIが客観的なデータや情報を構造化して提示することで、人間はより質の高い仮説構築や創造的な思考に集中できます。
例えば、レガシーコードの事例では、コードという「データ」を可視化することで、属人的な解読作業から脱却しました。今後、営業支援AIのようなツールが実現すれば、市場データや過去から蓄積した独自のデータ等、様々なデータに基づいた提案が可能になるでしょう。このように、データに基づいた客観的な土台をAIが用意し、人間がそのうえで高度な判断を行うという協業スタイルが、業務の質そのものを変え、特に若手社員の成長を加速させる効果が期待されます。
「バイブ・ドキュメンティング」は、2025年8月から他部署へのPoC(Proof of Concept:概念実証)展開が始まります。まずは法人営業部門、リスク管理部門、商品企画部門等、文書作成業務が多い部署から順次導入される予定です。デジタル戦略部での取り組みにより蓄積されたツールの活用方法や効果測定の知見をベースに、各部門の特性に合わせたカスタマイズを行いながら展開していきます。
さらに今後は、現在の文書作成支援から一歩進み、データ分析や予測、判断のサポートまでを視野に入れた「意思決定支援」へと進化させていく計画です。また、個々のツールの進化だけでなく、それらを統合的に活用するための組織的な取り組みも強化されています。
藤井:私たちがめざすのは、AIと人間が互いの強みをいかしながら共創する環境です。AIは定型作業や情報処理を担い、人間は創造性、共感性、倫理的判断といった独自の能力を発揮する。こうした人間×AIの協働が、〈みずほ〉の未来の働き方を形作ると考えています。
藤井が語るように、〈みずほ〉の「Work with AI@MIZUHO」と「バイブ・ドキュメンティング」の取り組みはまだ始まったばかりですが、今回ご紹介した事例は大きな可能性を示しています。単なる効率化ではなく、業務の本質的な変革と価値創造をめざすこの試みが、〈みずほ〉全体、そして金融業界全体にどのような影響を与えていくのか、今後の展開にご期待ください。
※所属、肩書きは取材当時のものです。
文・写真/みずほDX編集部