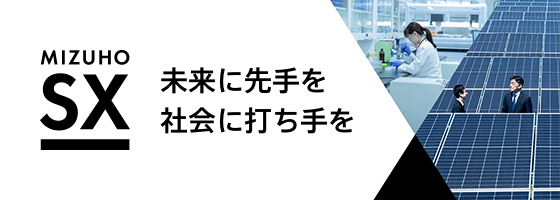Qiita Night開催レポート後編
「3社の生成AI推進担当者によるパネルディスカッション」
2025年7月8日
- FGみずほフィナンシャルグループ
OVERVIEW
エンジニア向け情報共有コミュニティサイト「Qiita(キータ)」では、プログラミングに関する知識や技術の共有ができる他、第一線で活躍するエンジニアが技術知見を共有し合うトークイベント「Qiita Night」も定期的に開催されています。そんな「Qiita Night」に今回〈みずほ〉も初参加し、2025年3月26日に、「Qiita Night~企業における生成AI活用~」が開催されました。
イベントでは、デジタル企画部AIX推進室でヴァイスプレシデントを務める齋藤悠士が登壇し、ライトニングトークを繰り広げるとともに、KDDI社とLIFULL社のAI推進担当者を交えたパネルディスカッションも行われました。
MIZUHO DXでは、当日のレポートを前後編に分けてご紹介。本記事(後編)は、Qiita社の清野氏をモデレーターに迎え、〈みずほ〉の齋藤、KDDIの河路氏、LIFULLの廣瀬氏による3名のAI推進担当者が熱い議論を交わしたパネルディスカッションの模様をお伝えします。
※本レポートは、当日のトーク内容の中からポイントとなる部分等を抽出して再編集したものです。
※所属、肩書きはイベント当時のものです。
INDEX
生成AIを社内でどのように広めるか?
導入への課題とその克服方法とは。
齋藤:ライトニングトークでお話しした内容以外でお伝えすると、2023年6月に導入した「Wiz Chat」という社内チャットボットがあります。当時はまだ世の中の生成AI熱も今ほど高くはなく、最初のうちは社内普及率があまり高くないことが課題で、それに対する施策をオンラインとオフラインの2軸で進めました。
オンラインの方は、社内SNSでチャンネルを作り、頻繁に投稿する等、まずは使ってみようという意識を醸成するためにポジティブな発信を継続的に行っています。オフラインでは、〈みずほ〉本部ビルの食堂やカフェで「出張DXカフェ」をやっています。そこで「Wiz Chat お悩み相談所」を開き、誰でも気軽に相談に来られるような、草の根的な活動をしています。
ITリテラシーや生成AIへの理解は人によって異なるので、こういった草の根的な活動は積極的に行っていくべきだなと。おかげさまで、最初のうちは数パーセントだった利用率も、直近は数十パーセントまで伸びています。
清野:2023年6月というと、まだ世の中的にも「生成AIをどうやって使うか」と探っている感じだったと思いますが、〈みずほ〉のような金融機関で早い段階から導入できた理由は何だったのでしょうか?
齋藤:生成AIの盛り上がりや勢いを、上手く力に変えようとしたのが大きかったですね。もちろん、セキュリティ周りをしっかりと安全・安心にしたうえで利用しないといけませんので、その辺りは社内でディスカッションを重ねて、しっかりと確認したうえでリリースしていきました。
清野:LIFULLさんとKDDIさんの取り組み内容についても教えてください。
廣瀬:LIFULLの生成AIプロジェクトは、本体の全従業員約800名が生成AIを活用し、自らの業務効率化を目的に始まりました。全社的に動き始めたのは2023年8月からです。プロジェクトチームは計6名で、そのうち4名は技術者、残りの2名は私を含めプロジェクトマネジメントや研修・教育に強い人事担当でした。環境の構築だけでなく、実際に従業員へと浸透させる部分までしっかりサポートする体制を整えました。
進め方としては、単に「このシーンで使ってください」というアナウンスではなく、各自の業務においてどこで生成AIが活用できるか、自ら考えて使ってもらうアプローチを採用しました。その際に発生した課題は大きく2つ。「使い方がわからない」という点と、機密情報が生成AIに学習されてしまうのではという懸念です。
前者に関しては徹底したレクチャーを通じて解決し、後者に関してはkeelai※1という社内チャットボットのリリースを通じて、社内の情報を一定レベルで安全に管理・利用できる環境を整え、心理的な安全性を確保しました。その結果、初期は約35%の従業員が生成AIを使っていたのが、1年後には83%にまで増加し、全従業員の業務時間において約42,000時間分、つまり全体の約3%の業務効率化を実現することができました。
河路:弊社もみずほさまの事例と似た動きで、2023年度の春頃から「KDDI AI–Chat」※2という名称で生成AIの業務利用を始めました。トップからの明確な指示のもと、5G通信やデータドリブン経営を軸に、全社員約1万人に対して活用促進を図っています。ただ「使え」と言うだけではなく、教育やコンテスト等の施策を継続的に実施して、徐々に浸透させる努力をしています。
よく使われるプロンプトがテンプレートとして共有される等基盤は整いつつありますが、業務改善の成果を得るためには、業務に特化したアプリケーションやサービスの開発も不可欠だと認識しています。例えば私自身が経験した事例ですと、特殊な領域のアンケートデータの集計画面で、どのように言葉をグルーピングすれば良いか悩んだ際に、事業部門の担当者と一緒に生成AIを活用して最適なプロンプトを考え、傾向把握を目的とした分析結果を得ることができました。これにより、業務効率化やデータ活用の実感が得られるという成果に繋がっています。
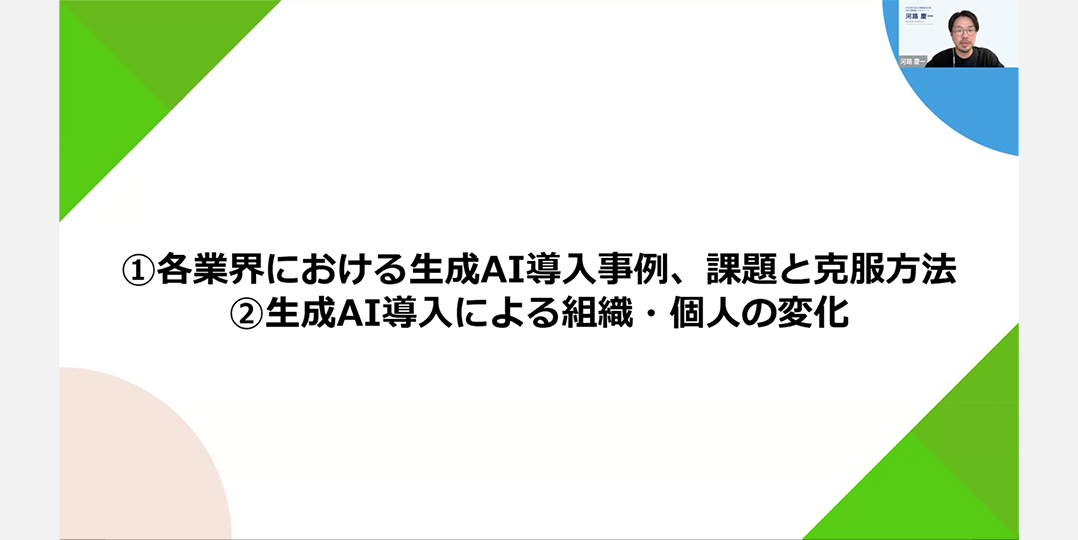
生成AI導入で組織と社員はどう変わる?
取り組みが広がる今、考えるべきこととは。
清野:3社とも現在に至るまで、取り組みが広がっていると感じますが、成功の要因は何だとお考えでしょうか?
齋藤:トップダウンとボトムアップの両面があると考えています。トップダウンでは、ムーブメントを持続させるために、定期的に経営層向けのレクチャーや活動報告、最新のデモアプリ(面談記録作成AIや推論モデルを活用したチャットボット等)の紹介を実施し、経営層からの後押しを得ています。
一方、ボトムアップでは、先ほどもお伝えしたDXカフェや社内SNS、また2023年に実施した「生成AIアイデアソン」で2,000件以上のアイデアを集め、その中から優れたものをピックアップして実際に開発する等、社員自らの意欲を引き出す施策を行っています。特に、自分の意見が形になるという手触り感を大切にしていることが、成功の大きな要因だと感じています。
河路:弊社では、特にエバンジェリストのような熱意を持った人たちが積極的に引っ張っていくことで、気づけば全社で当たり前に使われている状態になっていると感じます。そう考えると、最初のムーブメントを起こす段階は終わっていて、今はむしろ定着と更なる高度な活用、例えば業務効率化がどの程度実現されているかを計測する段階に移っている印象です。
実際、異なる本部で既にAIが導入されているケースも多く、我々が想像していなかったようなアイデアが生まれる等、非常に面白い状況になっています。今後はどれだけ業務効率化が進んでいるのか、具体的な数字で示すための計測をしていきたいと考えています。
廣瀬:「生成AIを使ってね」と発信した際に、現状は、自発的に情報をキャッチし利用する人とそうでない人とで明確に2分しています。そこで、半期ごとに全従業員を対象にアンケートを実施し、どの程度活用できているかを把握しています。活用できている人からは良い事例を収集し、「Generative AI Award」(通称:GAIA)という月次の表彰制度を通じて全社に紹介することで、モチベーションを高めています。全体の15~20%ほどのメンバーは利用していないため、今後はその層への浸透もさらに重点的に取り組む必要があると考えています。
清野:また別の視点でお伺いします。生成AIを導入したことで、「考えなければならないこと」や「取り組むべきこと」が増えたという点について、もしあれば教えていただけますか?
齋藤:これまでは既存業務の単純な置き換えが主なテーマでしたが、今年からはAIエージェントの登場等のトピックもあり、従来とは異なる取り組みが求められています。特に、人口減少社会において労働力や社員数の減少が懸念される中、減少する社員数で業務を回すためには、AIを組み込んだ新しい業務体制を模索する必要があります。そのため、ビジネスユニットの業務プロセスを見直しながら、対話を通じて新たな働き方を探っていくことが、今後は求められるのではないかと考えています。
河路:生成AIを使うこと自体は悪くないと思っていて、これまでの業務知識や経験が豊富な社員が、AIを「相棒」や「コパイロット/副操縦士」として活用する、いわゆる壁打ちのパートナーとして使うというのは効果的だと思います。ただし、AIに頼りすぎるとアイデアを自ら考えなくなったり、生成された情報を鵜呑みにしてしまうリスクもあります。特に新しく入社する若手には、そこに至るまでの基礎的な業務知識をしっかりと身につけてもらい、そのうえでどのようにAIを活用すべきかを育成していく必要があると感じています。
廣瀬:全体的な視点で言うと、「使える人」と「使えない人」のスキル差が、今後広がっていくだろうなと感じています。生成AIはこれからポータブルスキルになり、パソコンの基本操作と同じくらい必須のスキルになると考えています。そのため、当社では今期から新入社員研修に生成AIの扱いを取り入れる等、早期にインプットさせる取り組みを進めています。
もちろん、業務のオペレーションの中に知らぬ間に組み込まれているみたいな状況も当然発生してきているとは思いますが、もし個人や部門、または会社が変わったときに、このようなスキルが身についていなければ、業務遂行に大きな影響が出るというリスクもあるでしょう。これを埋めることが、私たちが取り組んでいるプロジェクトの重要な役割だと考えています。
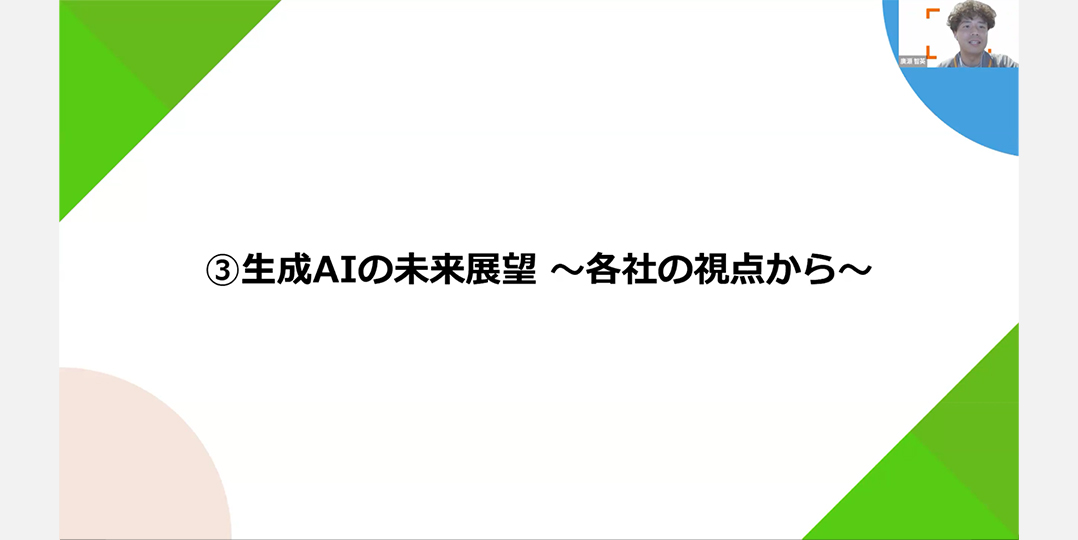
3社それぞれが見据える生成AIの未来。
清野:最後に、生成AIに対してこれからどのように取り組んでいくのか、展望をお伺いできればと思います。
齋藤:AIエージェントがエンドツーエンドで業務を代替する仕組みが、ようやく実現に向かってきていますので、従来の「バディ」的なサポート役から、能動的に動くAIへと進化させ、業務全体に組み込むことをめざしています。そのうえで、最終的にはエンドユーザーのお客さまに対して価値提供ができるAIを構築したいと考えています。
金融業界でお客さまに対してAIを展開するには、高いハードルが存在していると思っています。例えばプロンプトインジェクションにより意図しない融資の約束ができてしまう、ハルシネーションにより誤った回答をしてしまい取り返しのつかないことになってしまう等のリスクが考えられます。このようなリスクをしっかり管理して乗り越えた先に、利便性の高いサービスを提供できる未来を描いています。
河路:生成AIの活用が社内に浸透してきている状況ですが、まずは業務の中でどれだけ価値が創出されているかを「見える化」し、着実に実績を積み上げることが重要だと考えています。また、社外のお客さまに対しても、生成AIを活用したサービスやアプリケーションを提供する流れが進んでいます。技術力や実績に基づいて、リスク管理を徹底しながら、確実にお客さまへ価値を届けていくことが必要になるかなと思っております。
廣瀬:この1年半にわたる社内での浸透活動を通じて、業務効率化の成果を数値で捉えながら取り組んできたわけですが、効果を最大化するためにどのようなバランスで使うべきかというのは、引き続き追求が必要だと感じています。というのも、何でもかんでも生成AIに依存すると、場合によっては大きなミスを招いたり、成果がマイナスになったりするリスクもあります。
また生成AIは今後、企業内の共通スキル、いわゆるポータブルスキルとして、社員のキャリアアップやエンゲージメントの向上にも寄与すると考えています。そのため、社内研修等で早期に習得させ、どの職種や企業でも横断的に活用できるスキルとして定着させることが、持続的成長に繋がると信じています。
以上がパネルディスカッションの内容です。業界は異なりますが、いずれの企業でも生成AI推進の担当者にとって、技術的な課題だけでなく、「いかに多くの社員に活用してもらうか」が大きなテーマであることが浮き彫りになりました。〈みずほ〉でも、こうした課題に真摯に向き合いながら、今後も技術と人の両面から生成AIの活用を一層推進していきます。
PROFILE
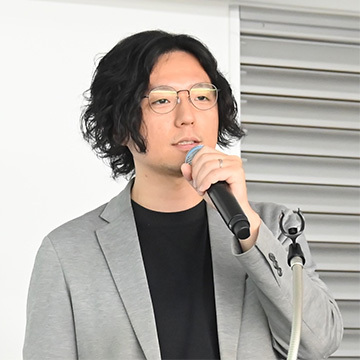
みずほフィナンシャルグループ
デジタル企画部 AIX推進室 ヴァイスプレシデント
齋藤 悠士
2012年より、国内金融機関にて融資審査・途上管理、現金輸送ロジスティクス、ATM出店計画策定等に従事。2017年より、国内ネット系銀行にて預金プロダクト担当として事業計画策定、ターゲティング分析、販促キャンペーン企画・実行を遂行。事務企画担当として当局対応、次世代システム更改要件定義、銀行アプリUI/UX改善等を経て、内製アジャイル開発チームの開発リーダーとして法人口座開設オンライン化プロジェクトを完遂。2023年9月より現職。現在は生成AIを利用したアプリケーション開発のリードおよび内製アジャイル開発の運営管理に従事。国内金融機関へアジャイル内製開発を普及・浸透させ、機動性確保・開発費抑制・UI/UXの先鋭化を実現することが目標。
撮影/河嶌太郎

KDDI株式会社
事業創造本部 Web3推進部 エキスパート
河路 慶一 氏
2009年にKDDI株式会社へ入社。運用部門での保守運用業務や開発部門でのプロジェクトマネージャ業務を経験した後、2013年から同社内でのアジャイル開発の立ち上げ、推進チームにエンジニアとして参加。以降アジャイル開発一筋でエンジニア、スクラムマスターとして様々なプロジェクトを推進。現在はプロダクトオーナーを支援してアジャイル開発で事業を成功に導く役割として、主にXR技術や生成AI等の技術を活用したプロジェクトを推進中。2022年からKDDIアジャイル開発センター株式会社へ兼務出向中。

株式会社LIFULL
グループ経営推進本部 経営戦略ユニット 日次採算性向上推進グループ長
廣瀬 智英 氏
2017年に株式会社LIFULLへ入社。同社の主力事業であるLIFULL HOME'Sの営業を担当した後、2018年10月より社内の労働生産性向上プロジェクト立上げに参画。その後現在に至るまで労働生産性向上に向けた戦術立案及び実行・制度設計・発信・社内コンサルティング等を担当。2023年7月から生成AIの活用を通じて業務効率化を実現する「軽量化プロジェクト」を立ち上げ、プロジェクトリーダーとして社内における生成AI活用の促進を担う。

Qiita株式会社
プロダクト開発部 部長
清野 隼史 氏
アルバイトを経て、2019年4月にIncrements(現 Qiita株式会社)へ新卒入社。入社後はQiita、Qiita Jobsのプロダクト開発や機能改善等を担当。2020年1月から「Qiita」のプロダクトマネジメントとメンバーのマネジメントを行う。2025年4月よりプロダクト開発部 部長として開発組織の統括を行う。
※所属、肩書きはイベント当時のものです。
文/長岡武司
編集/みずほDX編集部