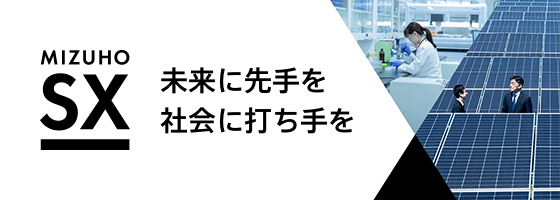上ノ山CDOが語る。
〈みずほ〉の新たな挑戦とDXで切り拓く未来。
2024年8月29日
- FGみずほフィナンシャルグループ
OVERVIEW
2024年4月、みずほフィナンシャルグループのCDO(チーフ・デジタル・オフィサー)に、上ノ山信宏が就任しました。本記事では、上ノ山CDOにインタビューを実施。〈みずほ〉のDXの基本方針、DXを推進する上での〈みずほ〉の強み、具体的な取り組みに加え、これまでのキャリアの歩みや、CDOという役職に懸ける想いや意気込みを聞きました。
INDEX

〈みずほ〉の強みや機能を集約し、
今まで以上の加速度でDX推進を実現する。
─DX推進により、〈みずほ〉がめざしていることは何ですか?
お客さまが抱えるお困りごとや社会課題を、デジタルやデータを活用して解決していくことです。〈みずほ〉のDX推進体制を強化するため、2023年4月には、グループ内に散らばっていた機能をCDOのもとに集約しました。あらゆる事業領域で、デジタル技術を有効かつ最適に活用し、DX推進に取り組んでいます。
─〈みずほ〉が進めるDX戦略の概要を教えてください。
DX戦略により実現していきたいのは、「最高の顧客体験の提供」「オペレーショナルエクセレンス」「成長する新規事業の創出」です。そのための戦略の柱として、①DX共通基盤の整備、②ビジネス・業務のDX化、③新規事業創出、という3点を掲げています。また、DXを推進する上での行動指針として、「常にお客さまと社会を中心に置き、国内外のAI等の最新技術を最適に活用し、全社目線・中長期目線で、めざす姿に向けて変化・挑戦を続ける」と定めています。
─2024年4月から上ノ山CDO体制となりました。力を入れている取り組みには、どのようなものがありますか?
重点的な取り組みの1つ目は、AI・データ活用等、全社で取り組むべき領域における、CoE(センターオブエクセレンス)機能の整備・拡充です。2つ目は、お客さま向け・社内業務向けの両面で注力する領域・案件を選定してDXに取り組む点、3つ目は、先端テクノロジーのR&Dを強化する点です。
また、2024年4月には、AI利活用の推進に特化した「AIX推進室」を設立。AI業務への適用とビジネスへの活用サポート、社内外プロモーション等を推進しており、〈みずほ〉のAI利活用を加速度的に進める様々な取り組みを行っています。
─DX推進において、〈みずほ〉ならではの強みは何ですか?
大きくは3点挙げられます。1つ目は、〈みずほ〉が持つネットワークの強さです。国内の8割の上場企業や高い技術力を持つスタートアップ企業4,700社とのお取引を持つ強固な顧客基盤に加えて、Google社やソフトバンク社等、大手プラットフォーマーとのアライアンスを持っています。2つ目は、みずほリサーチ&テクノロジーズやみずほ第一フィナンシャルテクノロジー等、グループ内に最新のデジタル技術やDXに関する知見を持つ会社があること。3つ目は、社員が自発的に挑戦するカルチャーやマインドがあることです。
─今後のDX推進に際して、上ノ山CDOが理想とする組織のあり方や、現在見えている課題について教えてください。
DX推進のためには、『水滸伝』に登場する「梁山泊※」のように、様々な経験や技量を持った、個性溢れる人材が集う状態になることが理想です。同時に個人の単独の力だけで成し遂げられるものではないので、ビジネスに対する知見、テクノロジーを使いこなす力、未来を見通す眼等、総合力を結集しないといけません。そのためにも、お互いが切磋琢磨し、更なる高みをめざしていける組織や体制を構築していく必要があり、それがこれからのチャレンジです。
※中国の歴史小説『水滸伝』に登場する108人の英雄達の集団のこと。「優れた人物たちが集まる場所」を指す言葉としても使われる。
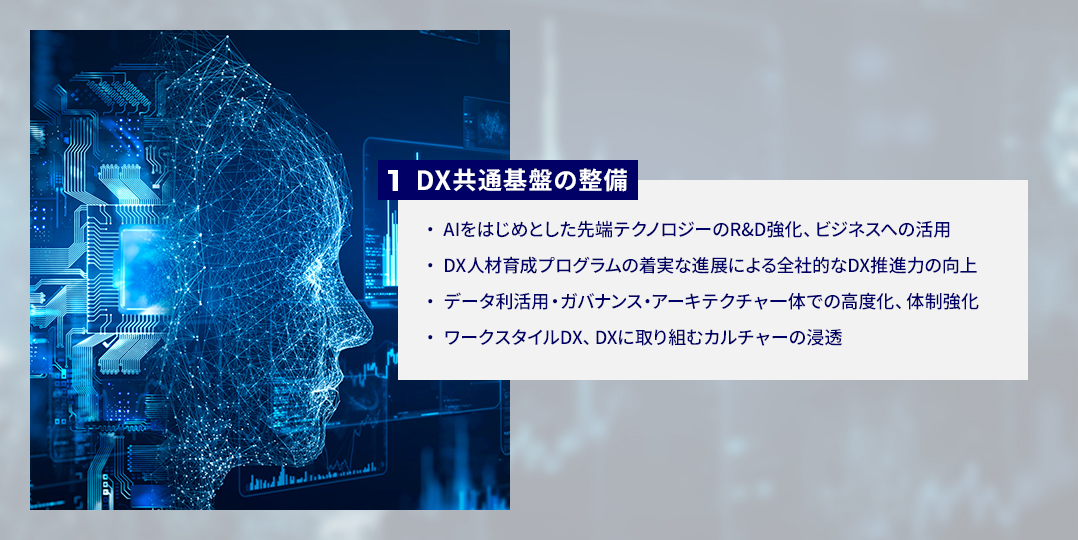
AIの活用や人材育成等により、
DX推進の原動力となる基盤をさらに強化。
─〈みずほ〉のDX推進における目標を3つ挙げてられていました。1つ目の「DX共通基盤の整備」に関して、具体的な取り組みを教えてください。
CDO傘下にある組織がCoE機能として、全社目線でDXを推進するための共通基盤の整備・拡充に取り組んでいきます。中でも重点的に取り組んでいるのが、AI利活用の推進とDX人材の育成です。前者は、「Wiz Chat」の導入や「生成AIアイデアソン」の開催、後者は「DX人材育成プログラム」という育成・認定制度の立ち上げや「データサイエンス・コンペティション」の運営といった、具体的な施策に結実しています。
─「DX人材育成プログラム」を立ち上げた理由を教えてください。
DXを全社的に推進していくためには、幅広い社員への教育が必要です。併せて、高度な専門性を持ったチームを組織することで、競争力を高める必要があります。〈みずほ〉はこれら2つのアプローチを同時に進めるために、2023年度に「DX人材育成プログラム」を立ち上げ、全社的な推進を開始しました。このプログラムは、高度なデジタル領域での専門性を有し、お客さまと〈みずほ〉の変革を推進できる「DX人材」と、DXリテラシーを有し、自らの業務に活用できる「DXベーシック人材」を、5段階で認定する制度です。
認定の取得者数は目標を超える勢いで推移しているものの、育成に必要な実案件での実践の機会を社内で十分に用意できていないという課題も出てきており、さらなるDX推進のために、課題への対応も含め、取り組みを強化していきます。
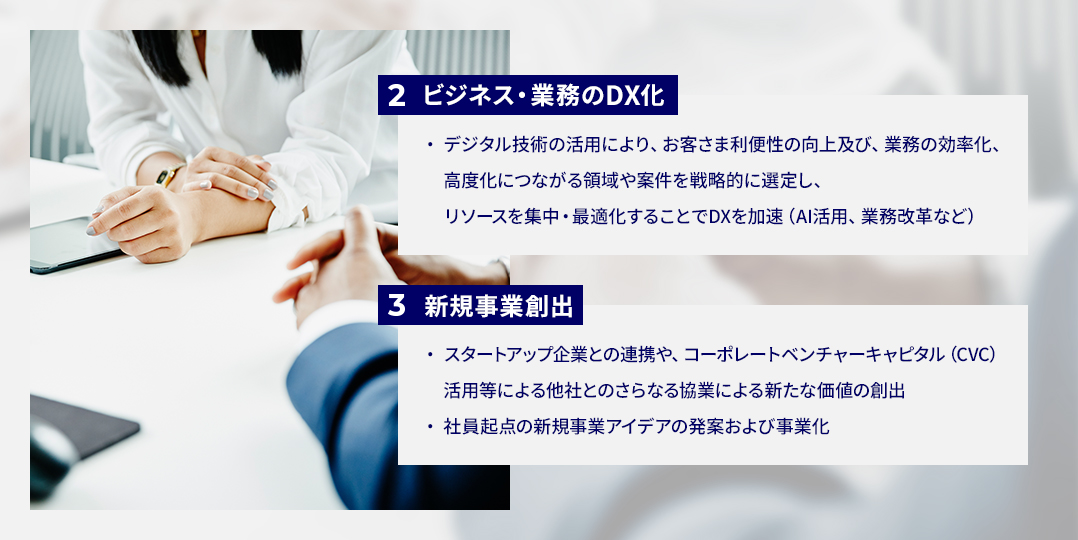
挑戦するカルチャーを醸成し、お客さまや
経済・社会の〈豊かな実り〉を実現する。
─〈みずほ〉のDX推進における2つ目の目標「ビジネス・業務のDX化」に関して、どのような取り組みを進めているか、教えてください。
「ビジネス・業務のDX化」では、デジタルを活用したお客さま向けサービス・チャネルの抜本的強化や営業担当の業務プロセス効率化、提案力の向上等に取り組んでいます。
具体的な例が、2024年5月に実施したみずほWalletアプリのリニューアルと、2024年1月から始まっているハイパーパーソナライズドマーケティングの運用です。
みずほWalletアプリのリニューアルでは決済手段を大幅に拡張したほか、各種銀行サービスとの連携を強化。リアル〈店舗〉とデジタル〈アプリ〉の融合を加速し、お客さまにより便利なサービス提供に努めていくのが狙いです。また、ハイパーパーソナライズドマーケティングとは個々のお客さまに対して最適なタイミング・チャネルで最適な情報を提供するサービスで、このようなサービス・チャネルの拡充により、お客さま一人ひとりのニーズに合わせた、最適な方法でのサービス提供を実現していきます。
─続いて、DX推進における3つ目の目標「新規事業創出」に関して、具体的な取り組みの内容を教えてください。
〈みずほ〉では、変化に先駆けて新たな価値を生み出すために、様々な形で新規事業やイノベーションの創出に取り組んでいます。また、この取り組みは、社内外・縦横のオープンな連携を生み出し、試行錯誤や失敗から学ぶ挑戦マインド等のカルチャーを醸成していくことにもつながっていくはずです。お客さまや社会のニーズをもとに生まれる新たなビジネスアイデアはもちろん、社員から事業アイデアを募る「みずほGCEOチャレンジ」や大企業・スタートアップ企業といったお客さまとの共創やアライアンス等、オープンな取り組みも行っています。
─Blue Labとみずほイノベーション・フロンティアの2社について教えてください。
Blue Labは、2017年に株式会社Wilを筆頭に〈みずほ〉等複数社が出資して設立した会社で、新規ビジネス開発に特化した組織です。独自の新規事業創出メソッドを活用しながら、外部とも連携しながらオープンなイノベーションを行っています。
一方、みずほイノベーション・フロンティア(以下「MHIF」)は、2023年4月に設立したコーポレートベンチャーキャピタルで、新規事業創出を資金面で支える役割を担っています。設立して1年で9件の出資を行っており、イノベーションの加速に貢献しています。2023年度から、この2社を含めた新規事業創出体制を整備し取り組みを開始しており、今後一層活動を活発化させていきます。
─社員限定ピッチイベントである「みずほGCEOチャレンジ」について教えてください。
〈みずほ〉では、「ともに挑む。ともに実る。」のパーパスのもと、企業風土の改革に取り組んでおり、挑戦を実践する社員の後押しに注力しています。「みずほGCEOチャレンジ」は、〈みずほ〉のそうした思いを象徴する取り組みのひとつです。
参加者は木原グループCEOや経営メンバーに直接プレゼンテーションを行い、採用されたアイデアには経営資源が割り当てられるほか、事業化に向けてはBlue LabやMHIFからの支援も行われます。
2023年3月に行われた「みずほGCEOチャレンジ」では、「Pochette(ポシェット)」というアイデアが事業検討案件として採用されました。これは、親子でお金の仕組みを学べるアプリや金融経済教育のプラットフォームを開発するというもので、現在は「みずほGCEOチャレンジ」事業化第1号として、2025年4月のサービス開始に向けて、テスト版の開発、実証実験等を行っています。

高い視座、広い視野で様々な可能性を見出し、
新しい価値を生み出していきたい。
─CDOに求められる役割は何だと考えますか?
CDOの役割とは、大きな方向感を示すことと、メンバーが働きやすい環境を整備すること。この2点に尽きます。その上で、独自に社外の人脈を構築し、ともに新しいチャレンジに挑んでいくことや、メンバーがプロジェクトを進めていく上で大きな壁にぶち当たったときに、経営レベルで議論を行い、突破口を切り拓いていくことも期待されていると認識しています。
─これまでのキャリアは、CDOという職務においてどのように生かされますか?
学生時代は数学が好きで、当時活況を呈していたデリバティブ領域で数学を活かした仕事がしたいと思い、金融業界の門戸を叩きました。ただ、入社後、最も長く従事しているのは人事の仕事です。この仕事で数学を使う機会はありませんが、逆に、数字では表しきれないヒトという存在の奥深さに触れることができますし、そこが人事という仕事の醍醐味でもあります。
CDO就任に際しては、理系出身という経歴が考慮されたと言われることもありますが、あまり関係ないと思います。お客さまや社会が抱える課題を解決するのは容易ではなく、様々な経験、知識、視点を持った人材が集まって、しかも自社だけでなく、同じ方向性を模索する世界中の英知を糾合していかないといけません。そうした多様性の文脈の中で求められるのは、文系/理系といった知識ではなく、様々な可能性を見出すための高い視座、広い視野ではないでしょうか。その意味では、メンバーとは少し違ったキャリアを持った私だからこそ、他の人とは違う見え方を提供できると期待されているのかもしれません。ともすれば同一質化しがちな議論をかき混ぜて、新しい価値を〈みずほ〉のみんなと生み出していきたいと考えています。
PROFILE
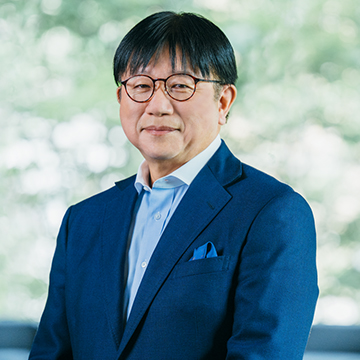
株式会社みずほフィナンシャルグループ
執行役グループCHRO兼グループCDO
上ノ山 信宏 氏
2019年みずほフィナンシャルグループ執行役員取締役会室長。2021年には、みずほフィナンシャルグループ取締役兼執行役グループCHROに就任し、グループ5社共通の新たな人事制度・運営への移行等を担当。2024年より、みずほフィナンシャルグループ執行役グループCHROに加え、新たにグループCDOを兼務。他に、みずほ銀行 常務執行役員 / みずほ信託銀行 常務執行役員を兼職。
※所属、肩書きは取材当時のものです。
文・写真/みずほDX編集部