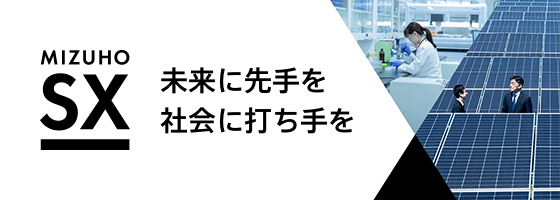AIは「脅威」ではなく「飛躍」のチャンス。藤井デジタル戦略部長が語る、人とAIが協働する未来の金融。
2025年10月24日
- FGみずほフィナンシャルグループ
OVERVIEW
生成AIの登場により、社会やビジネスのあり方が根底から変わろうとしています。この変革の波を、〈みずほ〉はどのように捉え、未来へとつなげようとしているのか。今回は、その取り組みを先導する、みずほフィナンシャルグループ執行役員デジタル戦略部部長兼デジタル・AI推進室長の藤井達人にインタビュー。〈みずほ〉が全社で推進する「Work with AI@MIZUHO」の思想から、AIが変える未来の銀行像、身につけるべきスキルまで、その壮大なビジョンを語ってもらいました。
INDEX
「飛躍」への羅針盤。〈みずほ〉のAI戦略を担うデジタル・AI推進室とは。
─まず、藤井部長のこれまでのキャリアと、現在の役割について教えてください。
これまで約25年間、外資系IT企業と日系の金融機関でキャリアを積んできました。テクノロジーと金融、双方の世界を経験してきた知見をいかし、現在はみずほフィナンシャルグループのデジタル戦略やAI活用推進の責任者を務めています。
─2025年4月に「AIX推進室」から「デジタル・AI推進室」へと組織を改編し、人員も増強されました。その背景と狙いは何でしょうか?
私たちは、AIを単なる効率化ツールではなく、「飛躍する絶好の機会」だと捉えています。このチャンスを最大化するためには、一部の部署だけでなく、グループ全体でAI活用を力強く推進するCoE(Center of Excellence:専門知識やノウハウを集約した組織)が必要でした。
そこで2024年4月にAI CoEとして「AIX推進室」を発足させ、2025年4月には「デジタル・AI推進室」として人員を倍増し、約70名体制へと拡充しました。私たちのミッションは、全社レベルの重点AIプロジェクトの旗振り役を担い、〈みずほ〉のAI活用の羅針盤となることです。
─「プロジェクト推進チーム」と「テクノロジー開発チーム」という体制を敷かれていますが、具体的な役割分担を教えてください。
「プロジェクト推進チーム」は、ビジネス部門と一体となり、重点AIプロジェクトを推進する役割を担っています。一方、「テクノロジー開発チーム」は、そうした取り組みを技術面で支えます。みずほリサーチ&テクノロジーズやみずほ第一フィナンシャルテクノロジーといったグループ内の専門人材を集約した「内製開発ラボ」を擁し、最新技術をリサーチしながら、ビジネスニーズに応えるAIアプリケーションを迅速に開発する体制を構築しています。この両輪が高速で回転することで、全社的なAI活用を牽引しています。

藤井 達人(みずほフィナンシャルグループ)
「作って、触れて、価値を体感。」
内製開発ラボが進める〈みずほ〉流AIシフト。
─これまでどのようなAIプロジェクトを進めてきたのでしょうか。主要な事例や成果を教えてください。
私たちの歩みは、2023年6月に導入した〈みずほ〉版テキスト生成AIアシスタント「Wiz Chat」から始まりました。そこから約2年、現在は業務効率化からお客さまへの提案支援まで、多岐にわたるAIツールの開発を進めています。
特に社員から好評なのは、会議の議事録を自動作成する「議事録作成AI」、自然言語で指示するだけでプレゼン資料を自動生成する「資料作成AI」、そして「Wiz Chat」の3つです。PoC(Proof of Concept:概念実証)では、「議事録作成AI」の活用によって議事録作成時間が70%以上削減され、一人当たり月4時間以上の時間創出につながったという結果も出ています。
こうしたツール提供と並行して、最も力を入れているのが「Work with AI@MIZUHO」という社内浸透施策です。これは、社員全員がAIを日常的に使いこなし、AIとともに働く文化を醸成するための活動の総称です。オンライン勉強会や、最新のAIツールに触れ、開発者と対話することができる「DXカフェ」といったイベントを通じて、「知る」「使う」「創る」のサイクルを回しています。
─AIプロジェクトを進めるうえで、大切にしていることは何ですか?
「まず作って、触れて、価値を体感してもらうこと」です。AIは技術の進化が驚くほど速く、数ヶ月で常識が変わります。その中で「こんなことができるはずだ」とスライドで説明しても、その真価は伝わりません。
そこで私たちの「内製開発ラボ」では、新しい技術を使ってすぐに動くアプリケーションのプロトタイプを作り、ビジネス部門の担当者に実際に使ってもらいます。その価値や課題をスピーディーに見極め、高速で改善を繰り返す。このアジャイルなアプローチが、変化の激しい時代には不可欠だと考えています。
─そのアジャイルなアプローチを実践するために、金融機関としてはまだ珍しい「内製開発」に力を入れているのですね。
ええ、多くの方にその点を驚かれます。ですが、決して「内製ありき」で考えているわけではありません。常に経済合理性や開発スピードを天秤にかけ、「作る」べきか、優れた外部サービスを「買う」べきかを冷静に判断しています。
そのうえで、私たちが戦略的に「作る」という選択をするのには、3つの理由があります。
1つ目は、「まだ世の中にないアイデアを、誰よりも早く具現化するため」です。AIを活用した新しい価値の創出は、まさに未知の領域への挑戦です。机上の空論で終わらせず、実際に動くプロトタイプでその可能性を確認して初めて、次のステップへ進むと感じています。
2つ目は、「コストパフォーマンスの追求」です。市販のソリューションありきで考えるのではなく、内製することで、同等の機能をより低コストで実現できる可能性があります。
そして3つ目は、「〈みずほ〉という現場へのフィット感」です。私たちの業務フローや企業文化に深く根ざしたツールでなければ、本当の意味で現場に受け入れられ、活用されることはありません。内製開発は、そのための最高の手段なのです。

AIは“副操縦士”。人が「人にしかできない価値」に集中する未来。
─ここからは未来に目を向けたいと思います。今後数年から10年先、金融業界でAIの進化や普及はどのように進むと考えますか?
金融サービスの提供スタイルが、お客さまのセグメントごとに大きく進化していくと考えています。私たちはその未来を見据え、「AIが変革する銀行の未来戦略」というレポートを策定し、203X年に向けたロードマップを描いています。
例えば、デジタルでの完結を求めるお客さまが多い個人向けの領域では、最終的に「AI対AI」の世界が到来するでしょう。お客さま一人ひとりが持つパーソナルAIエージェントに対し、〈みずほ〉のAIが最適なタイミングで最適な金融商品を提案する。そんな世界が2030年代には現実のものとなっているかもしれません。
一方で、中小企業のお客さまとのリレーションシップや富裕層のお客さまへのコンサルティングのように、「人間にしか提供できない価値」がより重要になる領域もあります。事業承継の悩みや、言葉にならない不安に寄り添うといった、深い共感や信頼関係に基づくコミュニケーションは、AIには代替できません。こうした領域では「人とAIのハイブリッド」な形が主流になるでしょう。
このように、徹底的に効率化・パーソナライズ化された「AI中心の金融」と、人間ならではの付加価値を追求する「人とAIのハイブリッド金融」が、それぞれの領域で深化していく。それが私の見る未来像です。
─なるほど。後者の「人とAIのハイブリッド」な世界では、顧客接点は具体的にどう変わるのでしょうか?
銀行員の役割が大きく変わります。AIが、人にとって非常に優秀な「副操縦士(Co-pilot)」になるのです。
例えば、法人営業を担当するRM(Relationship Manager:営業担当者)がお客さまを訪問する前に、AIが膨大な財務データや取引履歴、市場動向を瞬時に分析し、潜在的な経営課題や最適なソリューションシナリオを複数提示してくれます。
RMはその客観的なインサイトを手に、お客さまとの対話や、より高度な経営戦略の支援といった、人間にしかできない付加価値の高い業務に集中できるようになります。AIは仕事を奪う存在ではなく、私たちの能力を拡張し、より創造的な仕事へとシフトさせてくれる最高のパートナーになるのです。
─それを踏まえて、〈みずほ〉がめざす「未来の銀行・金融」のビジョンを聞かせてください。
私たちがめざすのは、「AIに任せられる業務はAIに任せ、人間はより人間らしい、創造的な価値創出に集中できる金融機関」です。
そのために重点領域を定め、それぞれの特性に合わせたAI活用のロードマップを描いています。
AI技術の力を最大限に活用し、業務の生産性を飛躍的に高めると同時に、人間だからこそ提供できる温かみや深い洞察力を磨き上げる。この両立こそが、〈みずほ〉がめざす未来の姿です。
─ビジョン実現に向けて、今後、AI・デジタル技術を活用して特に注力したい領域・テーマは何ですか?
先ほど挙げた重点領域の推進はもちろんですが、それらを支える技術基盤の強化が不可欠です。特に注力しているのが、〈みずほ〉特化型LLM(Large Language Models:大規模言語モデル)の開発です。
汎用的なLLMではなく、〈みずほ〉が長年培ってきた金融知識や業務ノウハウ、独自のデータを学習させたモデルを開発することで、より高精度で、私たちの業務に最適化されたAIアプリケーションを生み出すことができます。現在はオープンソースのモデルをベースに、この取り組みを加速させています。
また、将来的に何百、何千というAIエージェントが自律的に稼働する世界を見据え、それらを安定的に運用するための共通基盤「Wiz Base」の強化も重要なテーマです。
─AIの進化が進んだ将来を見据え、どのようなスキルやマインドセットが必要になるでしょうか?
最も重要なのは、AIを「仕事を奪う脅威」ではなく「能力を拡張する機会」と捉える前向きなマインドセットです。
そのうえで、具体的なスキルとしては「Work with AI」、つまりAIを当たり前に使いこなす能力が求められます。単にツールを使えるだけでなく、AIに的確な指示を与える「プロンプトエンジニアリング」の能力や、AIの強みと人間の強みを理解し、両者を最適に組み合わせる「ハイブリッド思考」が重要になるでしょう。
AIは、私たちの思考を助け、新たな視点を与えてくれる壁打ち相手にもなります。こうした新しいパートナーと、いかに協働していくかを考える力が、これからのビジネスパーソンにとって必須のスキルになると考えています。

AIとともに飛躍する未来へ。
〈みずほ〉が拓く、次世代の金融体験。
─最後に、今後の展望と、読者のみなさまへ向けたメッセージをお願いします。
生成AIは、金融機関のビジネスと私たちの働き方を根底から変える、巨大なポテンシャルを秘めています。〈みずほ〉は、この変化の波を恐れるのではなく、チャンスと捉えて果敢に挑戦を続けていきます。
私たちは「攻め」のイノベーションと「守り」のガバナンスを両立させながら、AI活用を進めてまいります。AIの力と、人間にしかできない価値の追求を通じて、これまでにない新しい金融体験をお届けします。
私たちの挑戦はまだ始まったばかりです。〈みずほ〉が拓く「AIとともに飛躍する未来」に、ぜひご期待ください。
PROFILE

みずほフィナンシャルグループ
執行役員 デジタル戦略部 部長 兼 デジタル・AI推進室長
藤井 達人
2023年キャリア採用でみずほフィナンシャルグループに入社。1社目の外資IT企業にて、メガバンクの基幹系開発、金融機関向けコンサルティング業務等に従事。2社目の外資IT企業を経て、総合金融グループではフィンテック導入のイノベーションを担当。その後、大手通信事業者の金融持株会社での執行役員、2社目の外資IT企業での業務執行役員を歴任し、現職。金融革新同友会「FINOVATORS」創立メンバー。『フィンテックエンジニア養成読本』(技術評論社)全体監修および共著。
※所属、肩書きは取材当時のものです。
文・写真/みずほDX編集部