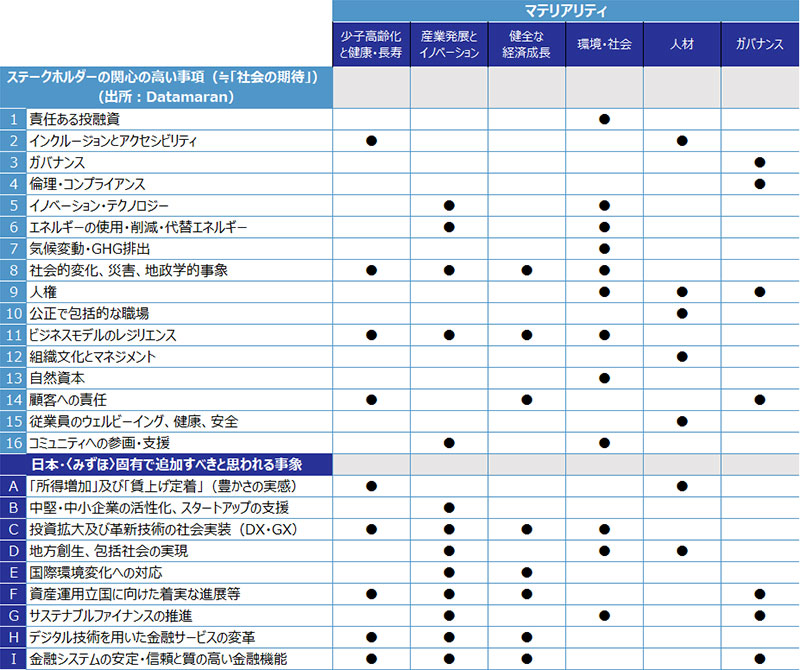マテリアリティ
〈みずほ〉は「マテリアリティ」を特定し、中期経営計画や業務計画に組み込むことで、グループ一体で「サステナビリティ」への取り組みを推進しています。
マテリアリティの定義
〈みずほ〉と、お客さま、社員、経済・社会をはじめとするステークホルダーの持続的な成長・発展にとっての中長期にわたる優先課題

リスクと機会・KPI・実績・アウトカム
| マテリアリティ | ステークホルダー | リスク・機会 | 主な取り組み | 代表的なKPI | KPI実績 | アウトカム |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
少子高齢化と健康・長寿 |
お客さま(個人) |
【リスク】 |
|
|
|
|
|
産業発展とイノベーション |
お客さま(法人) |
【リスク】 |
|
|
|
|
|
健全な経済成長 |
市場等 |
【リスク】 |
|
|
|
|
|
環境・社会 |
環境等 |
【リスク】 |
|
|
|
ESG(環境・社会・ガバナンス)面における持続可能性の向上 |
|
人材 |
社員・貢献の基盤 |
【リスク】 |
|
|
〈みずほ〉の人的資本の強化 社会全体への人的資本の強化への貢献 |
|
|
ガバナンス |
貢献の基盤 |
【リスク】 |
|
– | – | – |
- *社員意識調査【役員報酬KPI】におけるエンゲージメントおよびインクルージョンに関する各4設問に対する回答の肯定的回答率(1~5の5段階で4,5を回答した割合)
マテリアリティの位置づけ
〈みずほ〉の成長戦略は、〈ありたき世界〉からバックキャストした〈10年後の目指す世界〉をさらにバックキャストして策定されました。
マテリアリティは〈10年後の目指す世界〉を、ステークホルダーである「お客さま」「経済・社会」「社員」と貢献の基盤で区分し直したものです。
したがって、成長戦略とマテリアリティは10年を結節点として連関しています。
マテリアリティの実行計画は、成長戦略の「ビジネス面における注力テーマ」と「成長を支える経営基盤の強化」に織り込まれています。
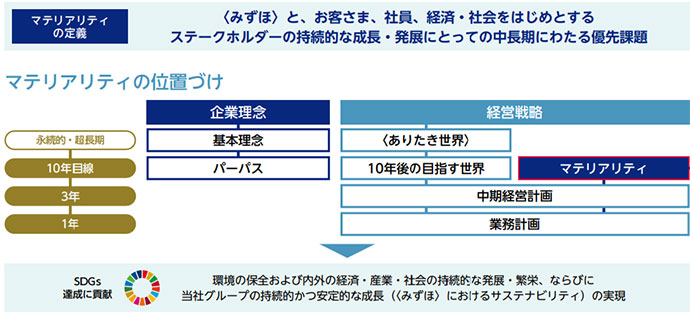
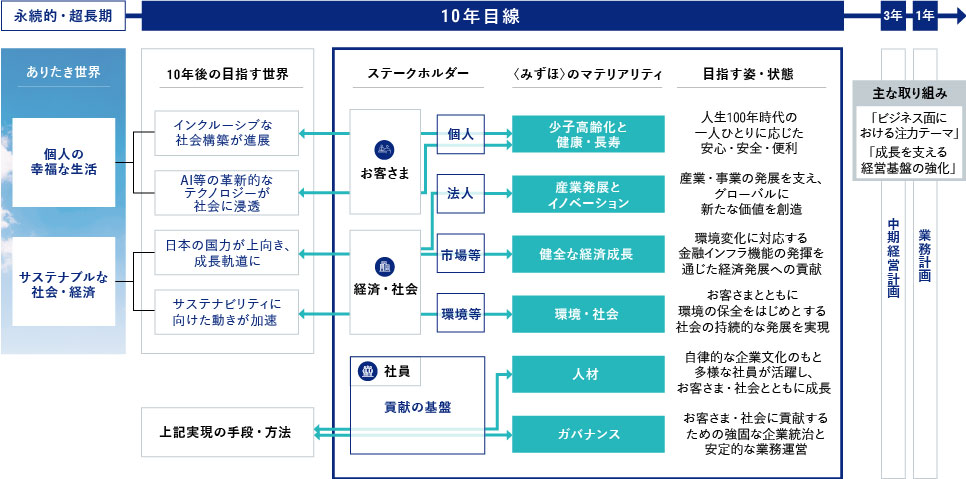
マテリアリティの特定・年次検証プロセス
「マテリアリティ」の特定にあたっては、社会の期待(〈みずほ〉が社会に与えるインパクトに対するステークホルダーの期待)と〈みずほ〉にとっての重要性(中長期的な企業価値への影響、〈みずほ〉の戦略・事業領域との親和性)を踏まえて検討しています。
なお「マテリアリティ」は、経営会議・取締役会を通じて、原則、年に一度検討しています。
| STEP1 |
「社会の期待」と整合しているかの確認
|
|---|---|
| STEP2 |
「〈みずほ〉にとっての重要性」と整合しているかの確認
|
| STEP3 |
リスクと機会、主な取り組みの確認・決定
|