鼎談 求められるサステナビリティ
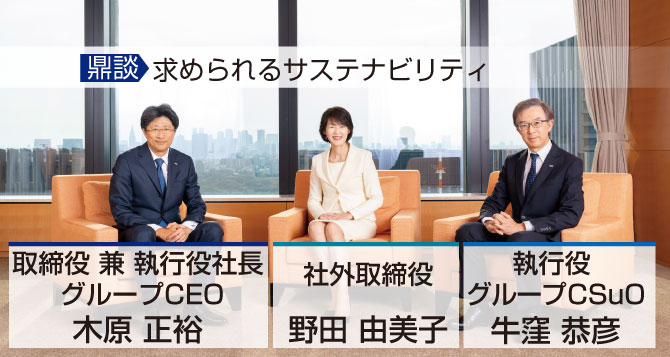
世の中で求められるサステナビリティについて、これまでの議論や取り組み、今後の課題等について、グループCEOの木原正裕、グループCSuOの牛窪恭彦、社外取締役の野田由美子氏の3名が意見交換しました。
サステナビリティを取り巻く環境認識
本日のテーマは「サステナビリティ」ですが、概念の広い言葉ですので、経営、ビジネス、社員や組織への浸透という3つの視点に沿って、意見交換をしたいと思います。まず、「経営」の観点ですが、サステナビリティを取り巻く世の中の環境について、様々な場での議論やこれまでのご自身のご経験を踏まえ、どのような課題認識を持たれていますか。
私が副会長を務めている経団連でも、「サステナブルな資本主義」の実現を理念に掲げ、サステナビリティを企業経営の中心的なテーマと位置づけ、取り組んでいます。サステナビリティに関して、私は3つの点が重要だと考えています。1つ目は、言うまでもなく、地球環境の保全です。もはや地球環境の存続すら危ぶまれる状況にあって、グリーントランスフォーメーション(GX)やサーキュラーエコノミー(CE)に向けた本気の変革が求められます。 2つ目は、社会のサステナビリティです。企業も社会的視座を持ち、公平・公正な社会の構築に向けて貢献することが大切です。例えば、人への投資を行ったり、サプライチェーン・下請け企業への責任を果たす等、社会全体をより良くしながら経営することが求められます。 3つ目は、サステナビリティの概念の複雑さです。何をもって「サステナブル」であると考えるのか、その判断は決して容易ではありません。例えば、GXには再生エネルギーやEV化が必要となりますが、そのために必要となる希少鉱物資源をめぐる地政学リスクの増大や生物多様性の毀損につながる可能性もあります。地域の雇用等社会への影響も考える必要があるでしょう。企業経営者は、こうした相反するいくつもの矛盾に対峙し、前に進んでいかなければならないのです。大きな挑戦に直面しています。
私も2024年1月にダボス会議に行った際に「サステナビリティは難しい」という捉え方が広がっていると感じました。野田さんが指摘された通り、「サステナビリティ」は切り口が増えています。環境・気候変動から、循環型社会、人的資本、人権に加えて、少子高齢化・長寿化が進むなかでは「健康」もサステナビリティの1つのテーマだと思いますし、インフレで日本でも「格差」が広がっていく可能性がある。これらのサステナビリティの課題に対して、〈みずほ〉はパーパス「ともに挑む。ともに実る。」のもとで今回の中期経営計画から、企業価値と社会価値の両方を創出すると掲げていますが、それは難易度が高いものです。
そこで「ともに挑む。ともに実る。」という精神は非常に重要だと思います。
社会に役立つ企業になるのであれば、まずは〈みずほ〉自身もサステナブルな会社になるために、我々もまた挑まなければならない。つまり、〈みずほ〉自身の経営体制を整備する必要があります。例えば、人的資本であれば、〈みずほ〉で成長した人が社会に出ていくことも歓迎しなければならないし、人権であれば人権デューデリジェンスをしっかりと取り組まなければならない。循環型社会への貢献であれば、自社の取り組みも当然に必要です。
〈みずほ〉自身の経営という観点では、トランジション(移行)へのリスクマネーの供給という金融機関としての役割を果たすことが重要と考えており、国や地域によってトランジションの進展には様々な違いがあるので、それぞれの状況に応じた社会やお客さまのニーズに丁寧に向き合い、「つなぐ」をキーワードに社会課題解決に貢献していきます。同時に、移行リスクもしっかりと認識していく必要があり、セクター自体が炭素高排出かということに加えて、それぞれのお客さまが事業を移行する意思・計画があるか、という点も含めて2軸で考え、サポートしていく必要があります。もう1つ重要なのは情報開示です。グローバルなサステナビリティ情報開示基準が導入されようとしており、日本におけるルールも議論中です。〈みずほ〉も対応を準備していますが、ただ規制に沿った開示を行うだけでなく、わかりやすく発信することも理解を深めるために重要だと感じています。
ビジネス戦略としてどう差別化を図るか
取引先の脱炭素支援は非常に重要ですね。企業経営者も羅針盤が無く迷っており、〈みずほ〉が経営者に寄り添い、ともに挑戦できるかがポイントではないでしょうか。さらに、20世紀の大量生産・大量消費・大量廃棄のリニアエコノミーからサーキュラーエコノミー(CE)への移行を実現するには、設計・製造・消費・回収・再生までのバリューチェーンをすべて変革しなければなりません。「革命」ともいえる転換です。しかし、欧州の若い世代は、人類の活動が既に「地球の限界」を超えつつあることに気づいています。2023年にブリュッセルでお会いした欧州委員会の環境担当コミッショナーは33歳で、「CEへの移行は当然のこと。やらない選択肢は無い」との考えをお持ちでした。CEの実現には、多くのプレーヤーを巻き込んだ連携が不可欠です。産業金融の雄である〈みずほ〉には、これらを「つなぐ」役割を担えるものと期待しています。
色々な当事者をつながないと、過去とは決別できません。〈みずほ〉で大企業を担当するコーポレート&インベストメントバンキングカンパニーに価値共創チームというチームがあり、金融バックグラウンドの社員に加え、商社から転職してきた社員もいます。発想力豊かに、お客さまと新たな事業を議論して出資をするのみならず、事業のプラットフォーム作りに一緒に取り組んでいます。例えば、インドに数多あるごみ廃棄場から代替燃料を製造する技術を持つスタートアップ企業に日本企業と一緒に出資しましたが、今後は、技術開発のみならず、廃棄物から代替燃料を製造するプラントが必要になってきます。そのようななかで、事業が拡大すれば、資金需要も出てきて、金融ビジネスとしても成長するでしょう。また、大企業のみならず、新たな事業のバリューチェーンを構築するなかで、中堅中小企業に、「つなぐ」ことの裾野を広げていきたいと思います。また、産業構造を変えていくことは非常に大きな話であり、グランドデザインを描く必要があります。それは独りよがりではいけません。様々な当事者と会話をし、グランドデザインを練り上げるということを、〈みずほ〉はやりたいと思いますし、やらなければならないと思っています。

まさにそれが〈みずほ〉の強みであり、挑戦して欲しいことです。私も銀行に勤めていましたが、銀行は「企業活動の結果である決算書を見て融資判断する」というスタンスになりがちです。これからは、多様なバックグラウンドを持った人材とお客さまとの幅広いつながりを活かし、より能動的な役割を果たしていただきたいですね。
決算書ではなく、企業の成長性を見るのが、新しい金融の在り方だと思います。日本政府はGX実行会議等で、産業の在り方や2040年ビジョンを真剣に議論しています。産官学の動きをどうつなげていくか、それに対して〈みずほ〉に何ができるか、ということを私も考えています。
2023年度は取締役会でも議論しましたが、サステナブルビジネス戦略を策定しました。カーボンニュートラルや循環型社会等が実現した将来を想像しながら、〈みずほ〉の強みがどのように貢献できるか、何をめざすのか、について、足元と中長期の両方の時間軸を含めて構想・発想していくことが必要だと思います。そのためには「調査」を重視する〈みずほ〉のカルチャーは重要な特徴だと思います。そして、足元の支援としてファイナンスも重要です。サステナブルファイナンスを2030年までに100兆円にするという目標は、〈みずほ〉の覚悟を示しています。また、みずほリサーチ&テクノロジーズのコンサルティング部門がインパクト評価を行う人的資本経営インパクトファイナンスを2023年度にリリースしましたが、既に10社に利用いただき、さらに多くの企業の関心を集めています。この「インパクト」は、社会貢献と企業価値のベクトルを合わせる考え方として有効です。また、中長期では、木原が紹介したような、レイターステージへの価値共創投資やアーリーステージを支えるトランジション出資枠等の投資・出資も重要です。水素では、2030年までに2兆円の資金供給することを宣言しました。日本政府が掲げた動きに対し、リスクマネーを供給することが金融の役割です。「つなぐ」ことについても、大企業を地方や中堅中小企業につなげる、もしくは、技術を持つ中堅中小企業を大企業につなげる〈みずほ〉でありたいと思います。さらには、サステナビリティは協調領域も多いです。競争相手と協調する領域であり、「ライバルの企業と手を組みませんか?」というきっかけとなる会話は〈みずほ〉にしかできないのではないか、と思っています。
では逆に、〈みずほ〉の課題は何でしょうか?
課題はグローバルです。サステナビリティのルール作りで先行する欧州の情報をつかむことや、海外で進むイノベーションを日本に紹介できること。これらを強化していきたいと思います。グローバルなサステナビリティのリテラシーや感度を上げていかなければならないと考えています。海外拠点の現地社員もいますが、日本へのインプリケーションをつかむという観点から日本からも派遣しています。
やることはたくさんありますが、何より重要なのは、今牛窪さんがおっしゃったような「覚悟」だと思います。誰も答えを持たない時代において、立ち止まらず前に進むためには、覚悟や勇気が必要です。木原さんも面談されたと伺いましたが、例えば、ユニリーバの元CEOのPaul Polman氏は20年以上前からサステナビリティを訴え続け、ぶれることなくユニリーバのサステナビリティ経営を進めてきました。〈みずほ〉にも、覚悟と勇気を持って挑む企業を支える金融機関であって欲しいと思っています。

まさにPaul Polman氏と面談するに際し、彼の著書『Net Positive』を読みましたが、彼のスタンスは「難しいから、やめる」ではなく、「難しいから、やる」ですよね。ファイナンスというのは、そのような企業の背中を押すものだと思っています。第一国立銀行も含めて様々な企業を創業した渋沢栄一の思いも同じだったのではないかと思います。当時、欧米には存在する産業や企業が日本には無い。日本で成功するかどうかは分からない。「分からない」からこそ支援する。これこそ、金融の役割だと思います。
社員へのサステナビリティの浸透について
そのように「挑む」ことは、一部の社員だけではできません。社員全員にサステナビリティの意識を浸透させる工夫について、ご自身の経営者としての経験から何かアドバイスはありますか?
私が所属する企業も、〈みずほ〉と同じく全国で事業を展開しており、社員も1万人近くいます。地域で働く現場の社員すべてにパーパスやサステナビリティを浸透させるのは本当に難しいことです。私の経験から大切だと感じるのは、トップからのメッセージのみならず、ビジネスラインのヘッド、そして部長・課長、営業所長と、それぞれのリーダーが自分の言葉でパーパスを語り伝えていくことです。そして、社員一人ひとりに、自分の仕事のなかで、パーパスやサステナビリティの意味することを考えてもらうことが重要だと思います。
色々なレイヤーでメッセージを発することが重要ですね。私も「CSuOダイアログ」として2023年度は約30回、営業部店で日々お客さまと接している社員を中心に会話をしました。嬉しい誤算であったのは、1~2年目の若手社員から「〈みずほ〉はまだまだやれるはず」「お客さまのサステナビリティに応えるソリューション提供ができずに悔しい思いをした。次はもっと良い提案がしたい」という声を聞けたことです。若い世代はサステナビリティの意識が高いということを目の当たりにしました。そこで2024年度には、〈みずほ〉自身をサステナビリティ色に染める、お客さまへのソリューションを提供する、という社員のアイデアや意見を募り実現していく、社員ワーキンググループを始動します。関係するセクターの大企業担当者や、大きなプロジェクトファイナンスを手がける部署、または政策提言を行う部署等だけではなく、社員全員がサステナビリティを自分事として捉えること。そうすることで、具体的に発想することができ、お客さまがまだ気づいていないサステナビリティのニーズを発掘できるようになれると思います。

消費電力の大きい半導体製造において、消費電力を削減できる素材を扱うスタートアップ企業への融資に取り組んだ事例があります。難易度の高い融資案件に挑んだ好事例として社内で取り上げられましたが、この事例はサステナビリティへの取り組みでもあります。「今、自分が手がけていることがサステナビリティにつながっている」と気づくこと、それを伝播することも重要だと思います。
まさに、社員一人ひとりが、たとえ小さなことであっても、自分の仕事がサステナビリティにつながっていることを発見し、実感できるとよいですよね。金融機関として、持続可能な経済社会の構築にどう貢献できるのか、〈みずほ〉として何ができるのか、これからも議論していきましょう。社外取締役として、〈みずほ〉の挑戦をともに支えていきたいと思っています。
本日はありがとうございました。