vol.14「人間エンジンの秘密」東弘一郎さんインタビュー
【はじめに】
爽やかな青空の下、見上げるほどの巨大な車が人の力でゆったりと動き出す。賑やかな七和地区(新潟県十日町市)を舞台にロマン溢れるパワフルな光景を繰り広げるのは、「人間エンジン」という大作だ。金属を用いて、人との関わりを動力とする立体作品を手がける作家、東弘一郎さんに話をうかがった。
【東弘一郎(AZUMA KOICHIRO):プロフィール】
1998年 東京都生まれ。卓越した金属加工の技術をもって主に人がかかわることで動く立体作品を制作している。代表作は、自転車を材料にした「廻転する不在」や、2023に韓国ACCで披露された「無限車輪」など。近年は、アジアを中心に海外でも積極的にグループ展に参加し注目を集めている。
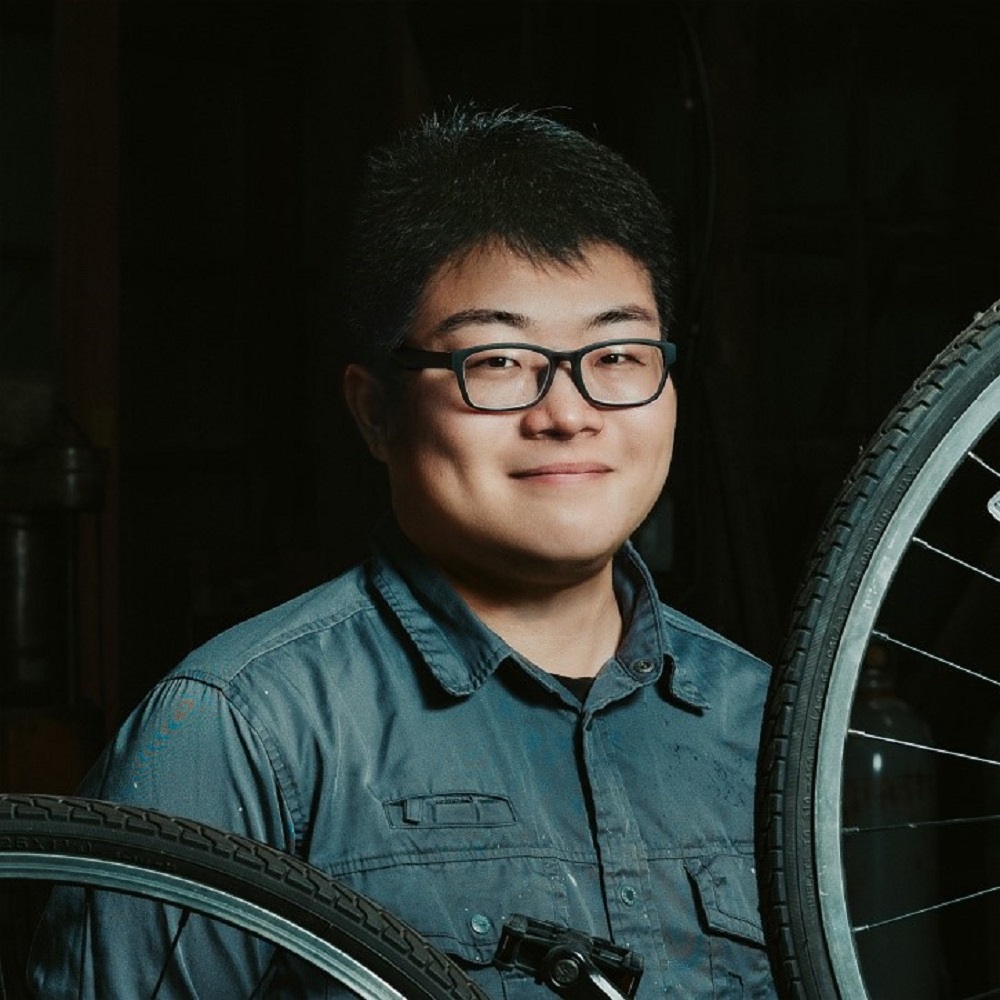
【地域と共につくること】
明るいオレンジ色の車体が特徴的な「人間エンジン」は、高さ4.5メートル、長さ7.9メートルに及ぶ大きな作品だ。にもかかわらず、なんと人の力を利用して走行させることができるのだという。
これまでにも人力によって動く立体作品を手がけてきた東さん。人力を作品の核とする構想や、地域と関わりながら制作を進めるユニークなプロセスは、いずれも過去の制作を通じて培ってきたものだという。その変遷について、少しだけ時間を遡って訊ねてみた。
「学部生の頃はお金がなくて、藝大取手キャンパス(茨城県取手市)周辺で使われなくなった自転車を材料に作品をつくっていました。取手は市内に競輪場があり、昔から自転車との縁が深い町なのですが、高齢化に伴って自転車の利用者が減ってしまっていたんです」
町の人々に声をかけて自転車を集めてまわり、地域を舞台に作品をつくる経験は、東さんがそれまで抱いていた〈美術作家〉のイメージに、大きな影響を与えることになったという。
「それまで自分が抱いていた美術作家のイメージは、秘密基地のようなクローズドなアトリエにこもって作品をつくり、展覧会でばっと姿を現すようなものでした。しかし取手市内の町中で作品をつくっていると、完成する作品がどんなものなのか周囲の人は既に知っていて、出来上がったものを興味津々に覗きにきたりするんです。そんなローカルな関わり合いが面白いなと感じるようになりました」

【人の力で動くこと】
その後に修了制作として発表した立体作品「無限車輪」は、〈廃棄された自転車から抽出した56個の車輪が、作品上部のペダルを人力で漕ぐことで一斉に回り出す〉というダイナミックな構想を実現したものだった。それぞれの自転車とその持ち主との記憶をつなぐパーツ(車輪)が、一人の漕ぎ手の脚力によって再びゆっくり動き出すという仕組みだ。
この「無限車輪」をきっかけに、東さんは作品の動力が人間であることの興味深さに気づいていく。
「自分の作品の特性は『自転車を作品に取り入れること』ではなく、『人力を作品に取り入れること』なんじゃないか。そう思いはじめました。それから人力で動くものといえば、公園で見かけるブランコなどの遊具がありますよね。牛嶋均さんという、家業の遊具製造を手がけながら〈遊具〉をテーマに独創的な作品を発表されているアーティストがいらっしゃるのですが、牛嶋さんと共同でアート作品を制作できた経験は転換点だったと思います。遊具から派生する造形のアイデアを牛嶋さんからいただいたことで、人が乗れて動かせる立体表現の奥深さを意識するようになりました」
そのようないくつかの発見が「人間エンジン」の構想へとつながっていった。
【雪国のヒーロー】
「人間エンジン」は、新潟の十日町で開催された国際芸術祭〈大地の芸術祭〉に絡めて制作した作品だったと東さんは教えてくれた。独特なフォルムのモチーフとなったのは、ロータリー除雪車という、超豪雪地帯の十日町を走行する特別な車両だ。
「このロータリー除雪車は、雪国のヒーローのようなかっこいい見た目とは裏腹にとても危ない機械なんです。雪を砕いて掻き込む回転装置に人が巻き込まれる危険性があり、とにかく『見かけたら近づくな』と住民の間では恐れられています。地域の暮らしに欠かせないヒーローでありながら、安易に近づくことは許されない——。そんな相反する感情をまとう除雪車に対して、もっと自然に『かっこいいな』という気持ちで近づいてみたり、身近に思える機会があったらいいなと考えていました」
それから本作の正面に掲げられた〈七和〉の文字の存在も気になるところだ。実はこれは〈七和地区〉という、十日町のさまざまな集落の出身者や市街の住民が集まってできたニュータウンを指す名称で、住民たちが合併させたの二つの地域(本町七丁目/三和)から文字を取って生まれた造語だという。七和という地名は正式には存在しないものの、住民たちが独自にコミュニティを形成し、名乗りをあげているそうだ。地区の結束力が強く、活気に溢れる七和地区の人々に東さんは興味をもったのだという。
「パワフルな気質をもつ七和地区の人たちと一緒に、雪国のヒーローであるロータリー除雪車を面白がってもらおうというのが制作のきっかけになっています。芸術祭で七和の人たちと共に人力で大きな車を動かして、東京から来たお客さんに観てもらう。そしてそれを地域のお祭りのような形で使おう、ということですね」

【一人では成し得ないこと】
そんな「人間エンジン」は七和の人々の助力もあり、実際に4度にわたって公道を走る機会に恵まれた。
しかし、初回の試走と2度目の走行で作品の一部が壊れるというアクシデントに見舞われてしまう。その度に故障の箇所を修繕し、作戦を練り直してきたという。
そして、8月におこなった3度目の走行で初めてコースを完走。当初は少なかった地域の見物客も、走行を重ねるうちに徐々に集まり、賑わいをみせるようになっていった。
「作品の整備や修理には、東さん自身が運営するアーティストチーム〈株式会社あずま工房〉が一役買っている。設計に精通したメンバーの知見や、工房としての金属加工の確かな技術が複雑で巨大な作品の実装を支えているのだ。
「地域の人に話を聞いて故障の原因を特定したり、現地で引いた図面をもとに自社で製造し直した部品を輸送して、作品をアップデートしていきました。一連のプロセスを振り返ると、間違いなく一人ではつくれなかったですね。地域や社会と関わりながら生まれる芸術って面白いなと改めて思います」
美術作家としての制作と、自身の会社の運営という2つの活動に加え、この春からは筑波大学で教員としても働きはじめたという東さん。活動のフィールドに大学という場が加わったことで、自身の制作プロセスや思想をこれまでにない方法(論文や研究ノートという形式)で記録することできるかもしれないと語ってくれた。
地域の内部へ入り込み、町の人々と直につながりながら、集まった人の力を動く力に換えてゆく。人と人との関わり方が多様に問い直されるこの現代に、東さんの作品がみせる運動の軌跡は、特別な祈りのようにも映るのだった。

(構成/文:野本修平)
(写真提供:東弘一郎)