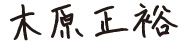CEOメッセージ

次の挑戦へ、整いつつある基盤
複雑に課題が絡み合う社会において、我々〈みずほ〉はどんな存在でありたいか。また、未来に向かってどんな社会を創造していきたいか。2023年度からスタートした中期経営計画を策定する中で議論を重ねてきたテーマです。
お客さまが様々な課題を抱え挑戦されている中で、お客さまの挑戦に寄り添う存在になりたい。その中で〈みずほ〉自身も様々な挑戦をしていきたい。さらに言えばお客さま同士の挑戦を「つなぎ」、課題解決のプラットフォームを構築していく懸け橋となりたい。そんな思いで制定したのが新しいパーパス「ともに挑む。ともに実る。」です。まさに「ともに」に我々の思いが詰まっています。私自身はこのパーパスを掲げて本当に良かったと実感しています。
ここで、私が実感を深めた2つの事例を紹介します。1つ目は価値共創投資。新たな産業・市場の創出に向けたお客さまの新規事業に対し、直接資本参加によりお客さまと事業リスクをシェアする取り組みです。2つ目はNISAカフェ。通常の店舗運営時間外に気軽にお立ち寄りいただけるカフェ形式の相談・セミナーを、とある店舗の社員の発案で開始し、それが全国的に展開していきました。いずれも、お客さまや社会のニーズに向き合い、ともに挑戦する〈みずほ〉のパーパスを体現した取り組みです。
また、渋沢栄一、安田善次郎そして結城豊太郎といった先人たちから受け継いできたDNA、すなわち、様々な人々と積極的に関わりながら、日本の近代化に貢献してきた「共創」の精神を踏まえ、我々がめざすべきは、「経済的価値にとどまらない社会的価値の実現」であることを改めて認識しました。そして、ありたき世界を「個人の幸福な世界」と「サステナブルな社会・経済」と定義し、10年後の目指す世界として以下を掲げました。「インクルーシブな社会構築の進展」「社会にAI等革新的なテクノロジーが進展」「日本の国力が上向き成長軌道に」そして「グローバルにサステナブルな社会」。1点目は誰もが健康で幸せな生活を送れる社会。2点目はテクノロジーの力で利便性と生産性が向上する社会。3点目は文字通り。そし4点目は渋沢栄一が掲げた共存共栄が実現する世界です。
そして10年後の世界観を実現すべく、我々が注力するビジネステーマを5つ、2023年度に決めました。①顧客利便性の徹底追求、②「資産所得倍増」に向けた挑戦(日本における資産形成・資産運用)、③日本企業の競争力強化、④グローバルCIB(コーポレート&インベストメントバンキング)ビジネス、⑤サステナビリティ&イノベーション。足元、米国の関税政策を受け、世界情勢の不確実性が高まっています。グローバル化を推し進めてきた世界に大きなパラダイムシフトが起きています。このパラダイムシフトが示唆することは何か。私自身は、各国が自らの強みや課題を再認識し、自らの勝ち筋を再構築していくことが求められるということだと思います。少子高齢化による人手不足、低い食料・エネルギー自給率、産業の国際競争力の低下といった課題を抱える日本は、今こそ国としての勝ち筋を再構築していく必要があります。そうした中で、我々の戦略の中核をなす5つの注力テーマは時代の要請に合ったものと確信しています。①から③はまさに日本の競争力向上をテーマとしています。国同士の利害が対立する中においても民間レベルで協働が重要になります。④は地域間の連携を通じてグローバルな協働を促進する機能です。そして、サステナビリティの重要性も不変です。我々はこれからもこの5つのビジネステーマを愚直に深めていきます。
一方、中期経営計画で掲げた財務目標は2024年度に前倒しで達成しましたので、2025年度より新たな中期財務目標をスタートさせています。昨今の経営環境は目まぐるしいスピードで変化しています。係る中、中期財務目標は3年間といった特定の期間に固執することなく、環境変化に応じて柔軟に見直すことで、ステークホルダーの皆さまとの透明性の高いコミュニケーションを築いていきたいと思います。
「目指すビジネスモデル」の進捗
さてここからは、5つのビジネステーマの進捗と課題、また就任以来進めてきましたカルチャー改革の状況をご説明します。加えて5つのビジネステーマとは別に、更なる成長に向けた全社レベルの課題についてもご説明します。
5つのビジネステーマにおける成果と課題
①顧客利便性の徹底追求(マスリテール)
ここ数年、みずほダイレクトアプリの改良を図ってきました。その結果、アクティブユーザー数は2022年度対比60%増加しました。また各種プロモーションの実施や、楽天カードとの提携により「みずほ楽天カード」を発行したことで、口座開設数は減少基調から増加基調に転じています。もっとも、他社対比での優位性を確保するには、より効果的なプロモーションの展開やユーザーの視点に立った導線の再構築等が必要です。この点、デジタルを基盤とする楽天に学ぶことが多いと、この1年間を通じて感じています。加えて、2025年3月にはUI・UXコンサルティングのリーディングカンパニーである株式会社ビービットとの資本業務提携を締結しました。この提携もてこに、一層の利便性向上に取り組んでいきます。
ダイレクトアプリの改良に加えて、コンタクトセンター・店舗についても多くの改良を実施してきました。コンタクトセンターでは2024年8月にAIを導入し、より迅速にお客さまのご質問やお悩みに対応できる体制を整えました。その結果、1件当たりの対応時間が減少し、お客さまへのスピーディな対応が実現しました。この領域は日進月歩であり継続的に改良を図っていきます。
一方で、店舗は、お客さまにとっての「来店しやすさ・相談しやすさ」を追求しています。引き続き、店舗・コンタクトセンター・ダイレクトの三位一体でお客さまの利便性向上に努めていきます。
②「資産所得倍増」に向けた挑戦(ウェルスマネジメント&アセットマネジメント)
政府による後押しもあり、お客さまの資産形成に対する意識は年々高まっていると感じます。一方で、資産形成や資産運用を始めることは、お客さまにとっては大きな挑戦です。そこで先述したNISAカフェを全国の銀行店舗で展開しました。その結果、NISA口座開設数はメガバンクの中でトップレベルに、49%出資する楽天証券も含めると本邦金融機関中でトップレベルの実績です。もっとも、ウェルスマネジメントビジネスを〈みずほ〉の差別化要素へと昇華させるためには、更なる磨き上げが必要です。楽天証券への出資により、資産形成層から富裕層に至る全顧客層へアプローチする体制を整備するとともに、対面とデジタル双方の顧客接点も確保しました。今後は、お客さまと接する個人RMの計画的・体系的な育成・教育とプロダクツラインアップの整備を図っていくことで、お客さまそれぞれのゴールに応じたコンサルティング提供を進めていきます。なお、プロダクツ整備の一環として、機関投資家や富裕層の関心が拡大しているプライベートクレジットについて、米国Golub Capitalに少額出資を行い同社が日本向けに設定する商品の独占販売権を得ました。今後もインフラや不動産等のプライベートアセットを投資対象とする商品拡充を進めていきます。
③日本企業の競争力強化(企業成長支援)
伝統的に我々は国内法人ビジネスにおいて強みを有しています。長い年月をかけて育んできた産業調査の力。各産業の将来像を業界各社と議論し、業界再編や個社の事業構造改革に寄り添ってきた歴史と知見。サステナブルな社会構築に向けて産業構造の転換が必要な中、ここは大きな強みとなります。この産業調査の強みを中堅企業にも展開し始めており、CEO/CFOの皆さまと活発に事業の発展や持続性を議論させていただいております。その結果、中堅企業向けのソリューション収益は確実に伸びております。加えて、事業承継支援・イノベーション企業への支援にも力を入れてきました。事業承継については、お客さまのニーズが多様化しています。後継者不足に悩む経営者の円滑な事業・財産の次世代への承継に対し、みずほ銀行・みずほ信託銀行・みずほ証券が一体となってワンストップのソリューションを提供しています。イノベーション企業支援については、特にディープテック領域へのリスクマネー供給に挑戦してきました。その結果、この領域での貸出残高は2022年度対比1.7倍となりました。

中国をはじめ海外との競争が熾烈を極める中、日本の産業の勝ち筋をしっかりと見極めていくことが不可欠です。中堅中小企業から大企業に至るまでの産業発展こそが国力向上の源泉であり、〈みずほ〉はその一翼を担う存在であり続けます。そのためにも、限られたリソースで生産性を上げていくことが必要であり、中堅中小企業ビジネスにおけるリソースアロケーションをより先鋭化していく必要性を認識しています。〈みずほ〉の存在意義を存分に発揮できると確信しています。
④グローバルCIBビジネス
我々は米国を中心にこの領域の強みを磨いてきました。2015年にRBSより北米貸出資産を購入し、その際に100名強のRM人材が〈みずほ〉のメンバーになりました。それ以来、DCM・ECM・デリバティブの機能を構築してきました。また、プライマリービジネスの成長の基盤となるセールス&トレーディングビジネスも顧客ニーズを起点に構築してきました。その結果、米州の業務粗利益は2022年度対比20%拡大しました。2023年には、米州でM&AブティックハウスGreenhillを100%子会社化しました。ミッシングピースであったM&A機能を手に入れたことで我々の投資銀行プラットフォームはおおよそ完成に近い形となりました。
〈みずほ〉のCIBビジネスの存在感は米国市場でも着実に浸透し、米国での求人応募数は飛躍的に増加。優秀な人材獲得がビジネスの更なる安定成長につながる好循環を創出しています。今後は、Greenhillを核に、日本・APAC・EMEA・米州の地域間連携を強めていくことで更なる成長を図ります。すでに良い動きが出てきています。日本と米州のバンカーの協働が飛躍的に拡大し、日米をまたぐクロスボーダーM&Aの数が増加しています。なお、グローバルCIBでは中期経営計画期間中、低採算アセットの削減に努めてきました。
⑤サステナビリティ&イノベーション
サステナビリティは、リスクと機会の両面を併せ持っています。ここではビジネス面での進捗をご報告します。それ以外の点は、2025年5月から7月にかけて発刊された各種レポートをご覧ください。
まず、2030年度までにサステナブルファイナンス組成額100兆円を掲げていますが、2024年度で40.3兆円まで順調に組成しました。またその過程で、中堅中小企業を支援する「GHG見える化インパクトファイナンス」、海運セクターの脱炭素移行を促進する「サステナブルシッピング・インパクトファイナンス」、カーボンニュートラルポート形成の促進に向けたサステナブルファイナンスフレームワークの策定支援等、各種の新しいファイナンス手法の導入に取引先と協働しました。サステナビリティ領域で注力する分野として、水素・カーボンクレジット・インパクト・サーキュラーエコノミーの4分野を掲げ、各分野で取り組みの進展がありました。足元の国際情勢の変化の中においても、サステナビリティ推進の重要性は不変です。〈みずほ〉は社会課題の解決と企業価値向上の両立をめざして、引き続き邁進していきます。
成長の推進力としてのカルチャー改革
グループCEOとしての私の使命は、健全なカルチャーの醸成と〈みずほ〉が強みを発揮し得る戦略の構築の2つと認識しています。健全なカルチャーが醸成されれば社員はモチベートされ挑戦する。〈みずほ〉が強みを発揮し得る領域に戦略を注力すれば社員が成功体験を味わうことで働きがいを感じ挑戦を繰り返していく。カルチャーと戦略の好循環が達成されれば自ずと〈みずほ〉が成長していく。このように私は確信しています。戦略につきましては前段でご説明しました。ここではカルチャー改革について簡単にご説明します。
カルチャーと戦略の好循環が達成されれば自ずと〈みずほ〉が成長していく。
我々がめざすカルチャーは、誰もが建設的な意見を発信することができて、活発な議論を通じて新たな取り組みや先進的なソリューション構築に挑戦できる風土です。そのうえで、あらゆるステークホルダーに対しオープンでフェアな姿勢で臨むことにより、〈みずほ〉がめざす世界をステークホルダーと「ともに」創造することです。
健全なカルチャー醸成には大きく3つのポイントがあります。1点目は、社員間の一体感を醸成するべくパーパスを定めること。すでにご説明した「ともに挑む。ともに実る。」です。2点目が挑戦する自立的な個人を育む人事制度。社員との協働で2024年度より新たな人事制度〈かなで〉をスタートさせています。役割と成果に応じた人事制度への変更です。日本的な年功序列から脱却し、より高い役割を担える人材は年齢に関わりなく登用していく。そして3点目が多様な人材が活躍できる風土をつくること。男女に関わりなく能力がある社員の登用や外部採用の積極化です。

カルチャー改革の先頭に立ち、秋田グループCCuO(Chief Culture Officer)とともに、年間100拠点以上の訪問、本社での15~20回のタウンホールミーティング開催を通じ、社員との対話を進めてきました。
こうした取り組みを通じてカルチャー改革も一定の成果があったと感じています。2025年度までにエンゲージメントスコア・インクルージョンスコア双方ともに65%まで引き上げることをお約束しましたが、1年前倒しでおおよそ達成できました。一方で、カルチャー改革に終わりはありません。継続的な取り組みを進めていきます。
持続的な成長に向けて乗り越えるべき全社横断課題
ここまでビジネステーマにおける成果と課題、カルチャー改革についてご説明してきました。今後は不確実性とボラティリティが高い状況が継続することが予想されます。また少子高齢化により労働人口が減少する一方で、テクノロジーの活用によりビジネスモデルそのものの変容を迫られる事態が想定されます。係る中、〈みずほ〉として無駄のない強靭な体制を構築するとともに、将来に向けて果敢に挑戦しビジネスの推進力を高めていく必要があります。このような視点で、今、解決しておくべき課題についてご説明します。
①組織構造の簡素化・最適化
組織構造が複雑化すると対話のロスや各種の管理コストが増加します。ここまでみずほ信託銀行の組織構造の簡素化やみずほ銀行・みずほリサーチ&テクノロジーズの統合に向けた検討等を推進してきました。グループ会社の更なる集約・整理やビジネスラインの簡素化等、もう一段の検討を進めていきます。
②コスト構造改革
急速なインフレ、国内における賃上げ、ベンダーコストの高騰、過去の資本蓄積フェーズにおける過少投資、規制対応等を受け、コストベースが大幅に拡大しています。いずれもやむを得ない事象ではあるものの、サステナブルな成長にはコスト構造のスリム化が不可欠と認識しています。徹底的な業務プロセス改革と商品サービスの改廃を推進するとともに、コンサルタントやSaaS等サードパーティー活用の妥当性検証を進めます。
③戦略とリソース配分の整合性確保
国内の労働生産人口の減少等により今後リソースは確実に逼迫していきます。投資について、戦略との整合性・投資効果を厳密に見極めたうえで取捨選択をしていきます。また、オペレーションの持続可能性や戦略遂行上の課題がある領域を中心に、狙いをより明確にしたうえで、人材の配置や育成を行っていきます。
④AI活用
全社レベルでAIの活用は進んできていますが、多くはプロセス改革にとどまっている状況です。従来の業務プロセスを根本から見直し、AIを「差別化の源泉」と位置付け、大胆な発想で変革に挑んでいきます。同時に、AIを当たり前のように使いこなし、新たな価値観を創出できる人材の育成にも取り組んでいきます。
全社横断課題については、猪股グループCSO、米澤グループCFOを中心にみずほフィナンシャルグループ全執行役のコミットメントのもと、全体最適の視点で進めていきます。
最後に — 異なる価値観を尊重し合える〈みずほ〉となるために
私がめざしているのは、「グローバルに展開する日本の金融機関」から、「日本の価値観に根差した、多様な文化をつなぐグローバル金融機関」への変貌です。
2025年4月、欧州証券現地法人CEOのBakhshi氏を持株会社であるみずほフィナンシャルグループの副社長執行役員に任命しました。グローバルな事業基盤を築いてきた〈みずほ〉ですが、海外人材を持株会社の経営層に登用するには至っていませんでした。先端的な金融市場で様々な経験を積んだ人材を経営の一員として迎えられたことは、世界と戦える素地が整った証左であると考えています。グローバルでも勝負ができる〈みずほ〉の象徴である今回の人事を端緒に、海外でキャリアを積んだ人材が〈みずほ〉のあらゆる部門・拠点で力を発揮できる、そうした組織づくりを加速していきます。経営層も含め〈みずほ〉全体に多様な人材が活躍し、あらゆる場面でグローバルな議論ができる。そのような金融機関をめざします。
めざしているのは、「グローバルに展開する日本の金融機関」から、「日本の価値観に根差した、多様な文化をつなぐグローバル金融機関」への変貌です。
5つのビジネステーマを深化させるとともに、社員と一体となりカルチャー改革を進めていくことで好循環を維持していきます。そのうえで全社レベルの課題に不退転の決意で臨むことで更なる成長の礎を築いていきます。引き続き温かいご支援をお願いします。